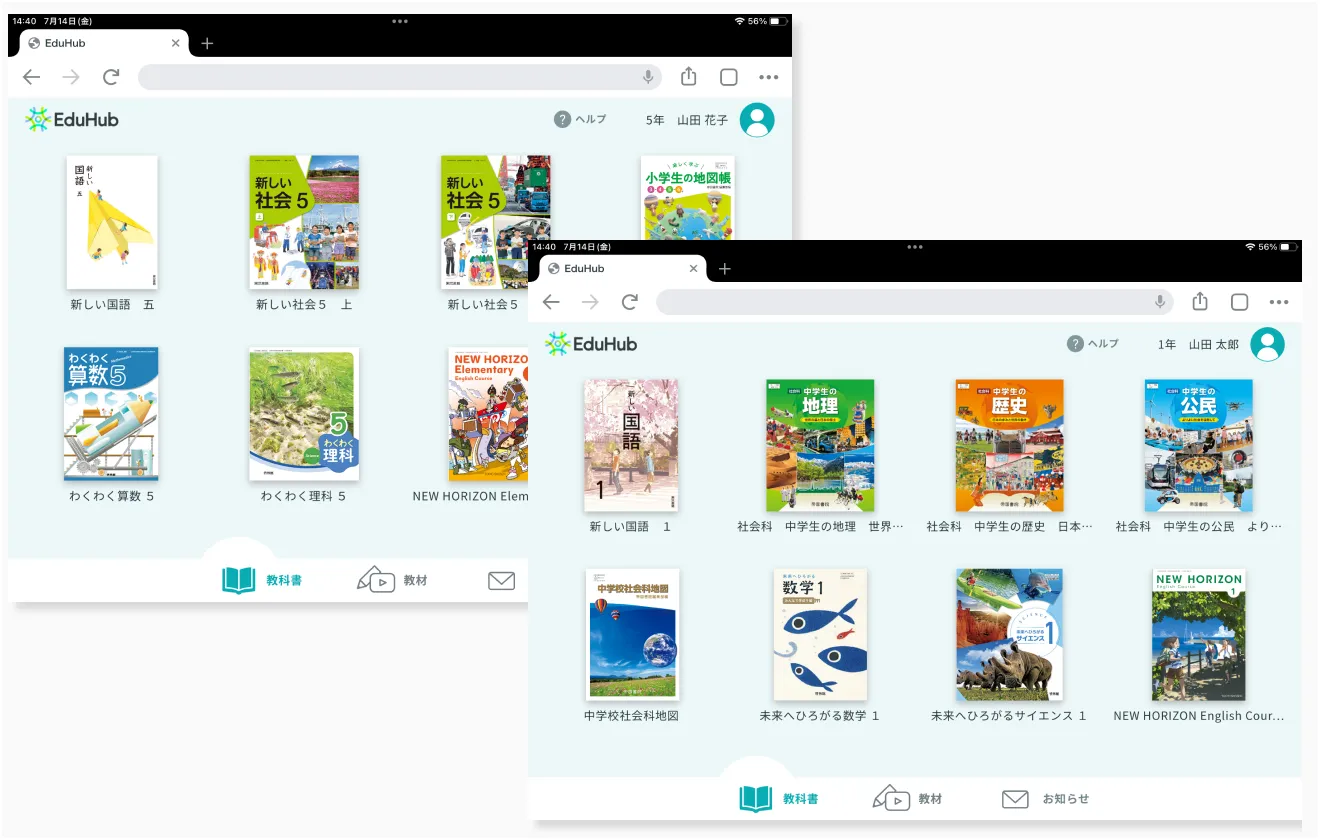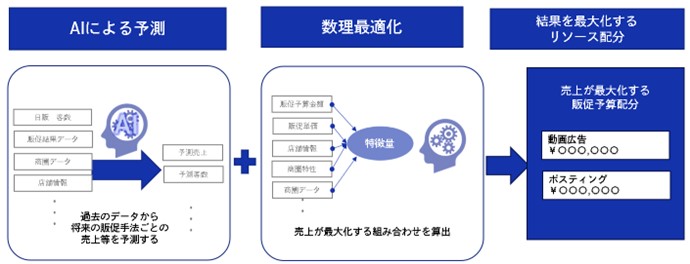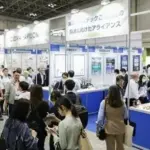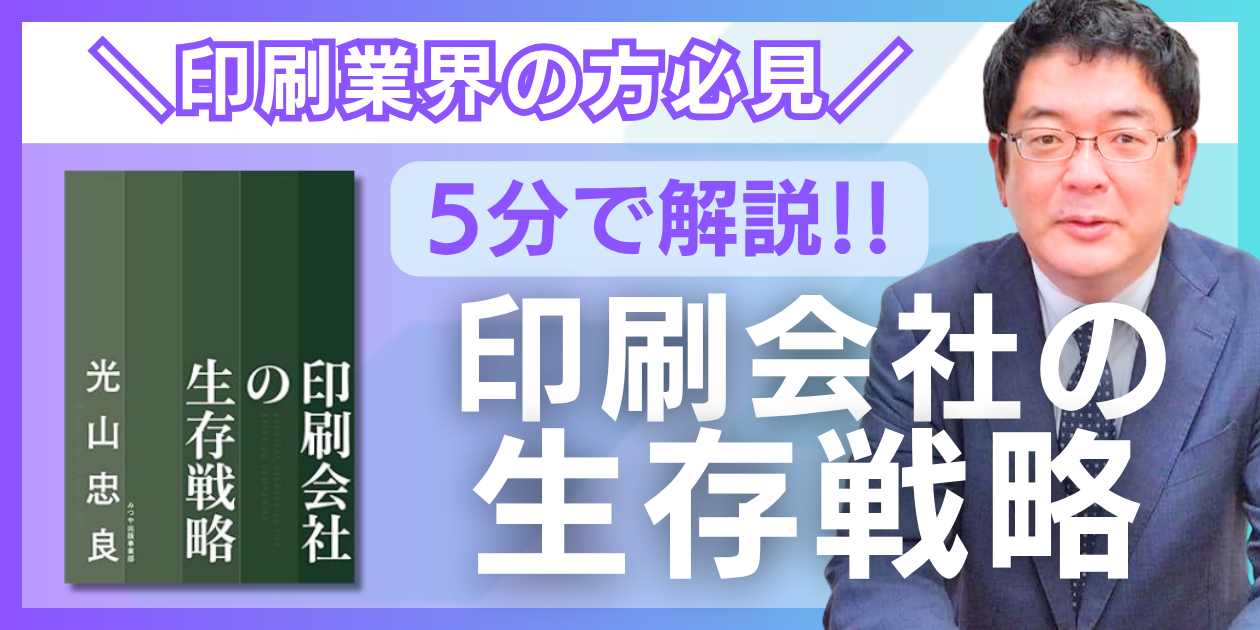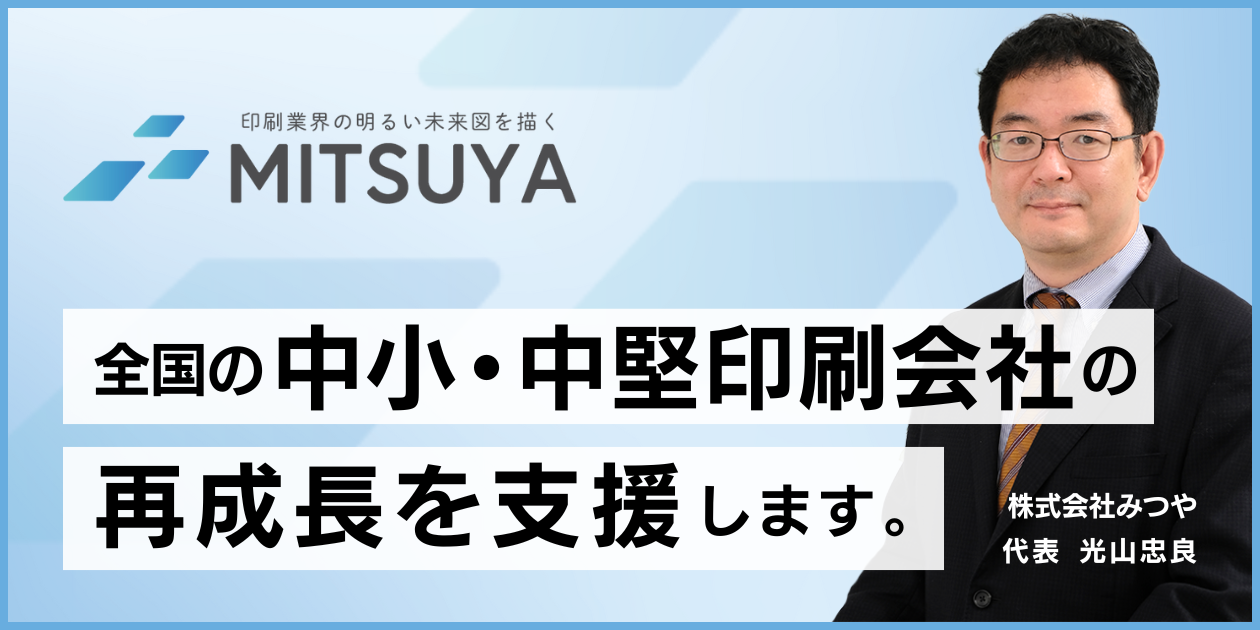リチャード・P・ルメルトは経営学の教科書には必ず出てくるし、重要な戦略家だけれども、その割には少なくとも日本ではあまり知名度が高くない気がする。マイケル・ポーターの「ファイブフォース分析」のような画期的なツールを生み出したわけでも、クリステンセンの「イノベーションのジレンマ」のような目新しい理論を提唱したわけでもない。三谷宏治氏の『経営戦略全史』では、ホンダの米国進出の失敗を予言して大外れした学者として紹介されている。
しかしルメルトの知名度の低さは、彼の主張の論理的帰着にも思える。ルメルトは安易な解決方法や、物事の単純化、一般化を嫌う。だからツールを提唱すること自体を嫌うし、目標管理を嫌えば、ミッションやパーパスなどを掲げることも嫌う。ちなみに一流の批判家だからこそ、ホンダの一見無謀な挑戦に対してネガティブな診断を下したのだろう。
本書の原題は「The Crux」(難所)である。実にルメルトの主張をうまく言い表しているように思える。彼のいう「戦略」とは「困難な課題を解決するために設計された方針や行動の組み合わせ」であり、「戦略の策定」とは「克服可能な最重要ポイントを見きわめ、それを解決する方法を見つける」ことである。本書にはコンサルタントとしての彼のアドバイスに肩透かしを食らった経営者がたびたび登場するが、派手なビジネスモデルも、おどろくべき発明も、汎用的なツールもない。自社の課題を見つけ、解決するという一見地道にもみえる作業こそが、彼の言う戦略策定なのである。
彼の真の価値は、その批判精神にあると思う。ポーターのファイブフォース分析は(よく初学者が誤解するように)産業の分析であって企業の分析ではないが(例えばファストフード産業に当てはまるのであってマクドナルド社に当てはまるのではない)、ルメルトによると産業と構成企業の収益性の相関関係は非常に低い。クリステンセンの「イノベーションのジレンマ」理論によく適用されるのはコダックの写真フィルム事業であるが、ルメルトによればコダックはデジタルカメラではなく新しいエコシステム(デジタル画像を共有し交換する文化)の前に敗れたのである。
「方針や行動の組み合わせ」と「克服可能な最重要ポイント」という言葉も肝である。ルメルトによれば、戦略は提示された選択肢から1つを選ぶことでもなければ、克服不可能な課題に挑むことではない。SDGsの矛盾した達成目標(焼き畑農業の撲滅と栄養失調の絶滅)や、アメリカのアフガニスタン戦略(親米勢力の支援と麻薬栽培の撲滅)までもがルメルトの批判対象である。
さて、私の感想である。ルメルトの主張には首肯すべき点も多い。というか拍手喝采したいところだ。日本企業のホームページを見るに、なんと空虚なミッションやパーパスが多いことか。短期的な数値目標に捉われていることか。大仰なビジョンに束縛されていることか。それよりも自社の課題にフォーカスし、一点突破すること、そしてそれを繰り返す地道な作業を行うこと、その方が結果的に成功に繋がる――その主張はおそらく一つの解である。
ただ、ルメルトはマイケル・ポーターの競争戦略論の(強力な)ライバルである。経営学の教科書にはRBV(リソース・ベースド・ビュー)という言葉で表現されているが、要はルメルトはいかに市場でポジショニングを取るかという外的要因よりも、自社のリソースをどう生かすかという内的要因に集中しすぎている気がする。
もうひとつは、一見矛盾する複数の課題を解決することこそ、真のブレークスルーのように思える。ルメルトは焼き畑農業と栄養失調の絶滅を矛盾する課題としているが、そうだろうか。焼き畑農業を根絶しつつ人類の栄養失調を克服するソリューションこそ、踏破すべき「Crux」(難所)なのではないだろうか。それをなしとげた企業こそ、真の勝利者になれると私は考えているのだが。
とはいえ、批判精神に満ちた同書は、達成不可能な売上目標を掲げ、四半期決算に怯え、ツールを使えばなんでも解決できると考え、空しいパーパスを諳んじるだけの経営者にとっては警鐘の書といえる。(光山忠良)