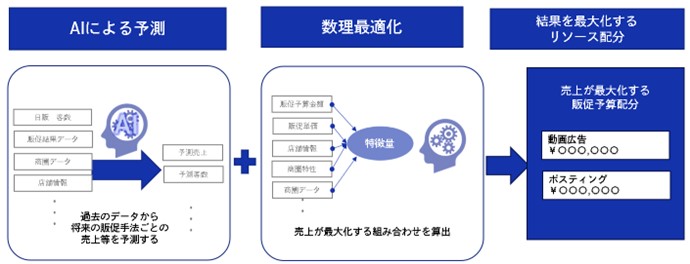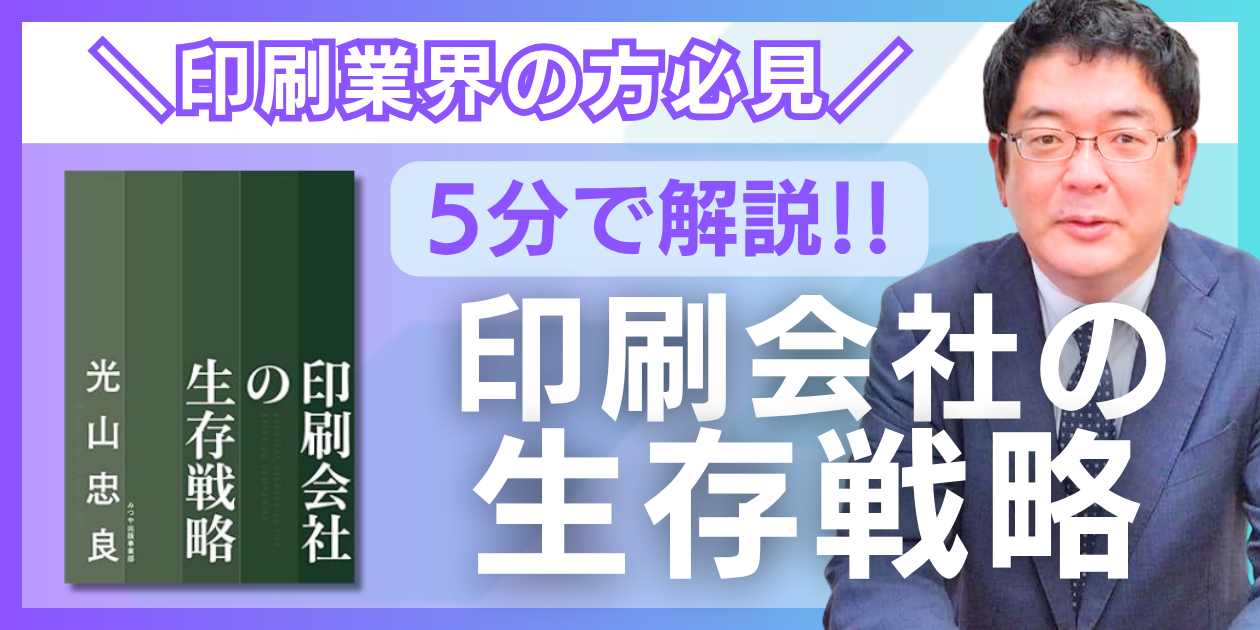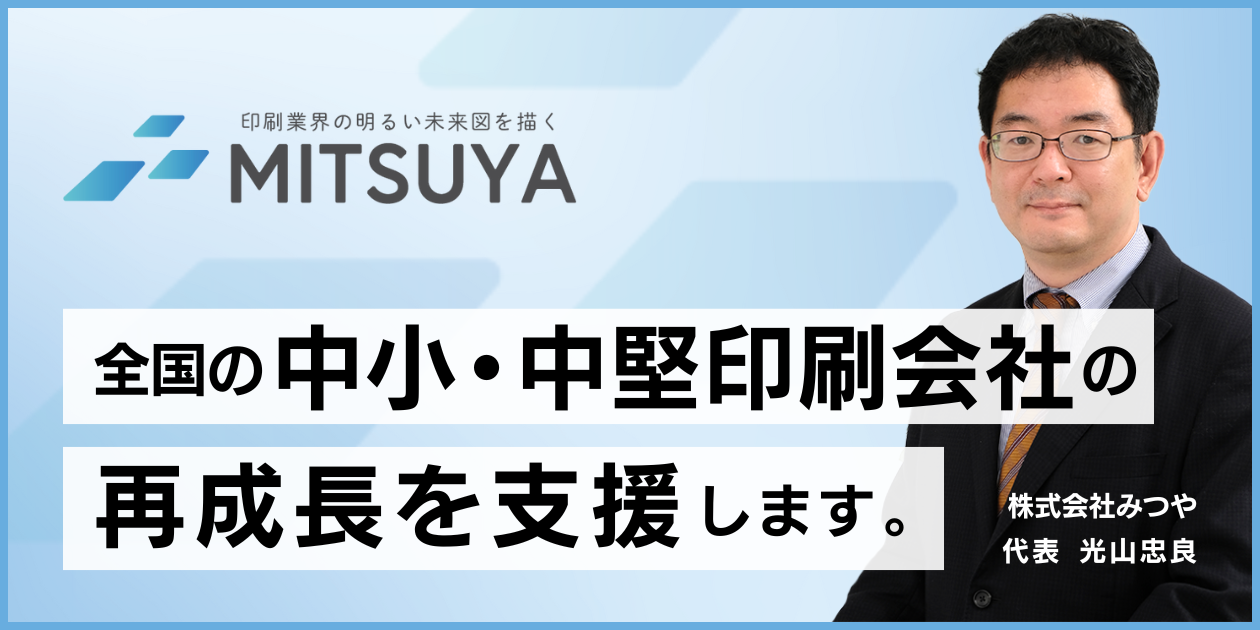アメリカ建国の父であるベンジャミン・フランクリン(1706-1790)が印刷屋から身を起こしたことは事実だけれども、当時の印刷屋を現在のIT企業のような新興ビジネスと喩えるのは無理がある。何しろグーテンベルクが活版印刷を発明してから300年が経っていた。印刷物がいぜん社会革命の大きな原動力であったのは間違いないけれども、それはフランス革命前夜にも、日本の太平洋戦争終戦直後にも言えるのであって、フランクリンの時代が特別だったわけでもない。

当時の印刷屋はすでに、蝋燭・石鹸職人と世間的地位は変わらなかった。資産家は印刷屋を営むにも芳しい名声を得ることはできなかったから、結果として最下層の者から徒弟を取って働かせた。ベンジャミン・フランクリンが徒弟として頭角を現したのは、並外れた単語や活字に関する知識と、並外れた体力によるものであった。フランクリンの大男ぶりと、彼の出世は無関係ではない。やがて上流階級のスポンサーを得て、フランクリンは印刷屋の経営者になる。
フランクリンは確かに経営者として財を成し、紳士階級の仲間入りをするのだけれども、彼が成功したのは印刷業としてではなく、新聞・出版業として、そしてジャーナリストとしてであった。彼の時代のころから印刷屋が出版者をコントロールする力を失っていたが、それでも彼は新聞やカレンダーを発行し、ベストセラーを生み出した。新聞業としては、政府の御用聞き記者には染まらず、鋭い筆致で不正を糾弾した。出版業としては庶民の心性に響く啓蒙的なカレンダー「貧しきリチャードの暦」を出版し、大ヒット商品となった。こうしてとびぬけた財を成したフランクリンは、その知性と身のこなしもあって、アメリカ政界の重鎮にまでのし上がる。
というわけで、政治思想家の宇野重規氏が『実験の民主主義』で著わしたような、印刷屋が市民革命前夜では新興ビジネスで、社会や国を動かしたというのは、アナロジーとしては面白いけれども、正確とは言えない。印刷屋は古くも新しくも、仮に職人技が重宝されたとしても、その特質上、下請け産業である。社会を動かしたのは出版物であって、印刷屋ではない。
何も下請け産業が悪いといっているのではない。しかし印刷機に固執しながら、下請け体質からの脱却を唱えていても、おそらく何も変わらない。フランクリンのように上流に進出し、コンテンツを生み出し、配信したことを、むしろわれわれ印刷業の未来へのアナロジーとすべきだと考える。
(歴史的背景から「印刷屋」と表現しました)
参考文献
ゴードン・S・ウッド『ベンジャミン・フランクリン、アメリカ人になる』
宇野重規『実験の民主主義』
ロバート・ダーントン『猫の大虐殺』