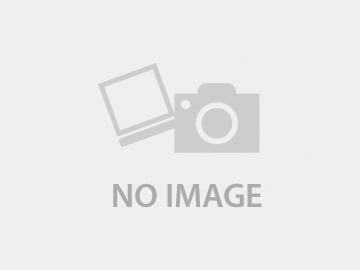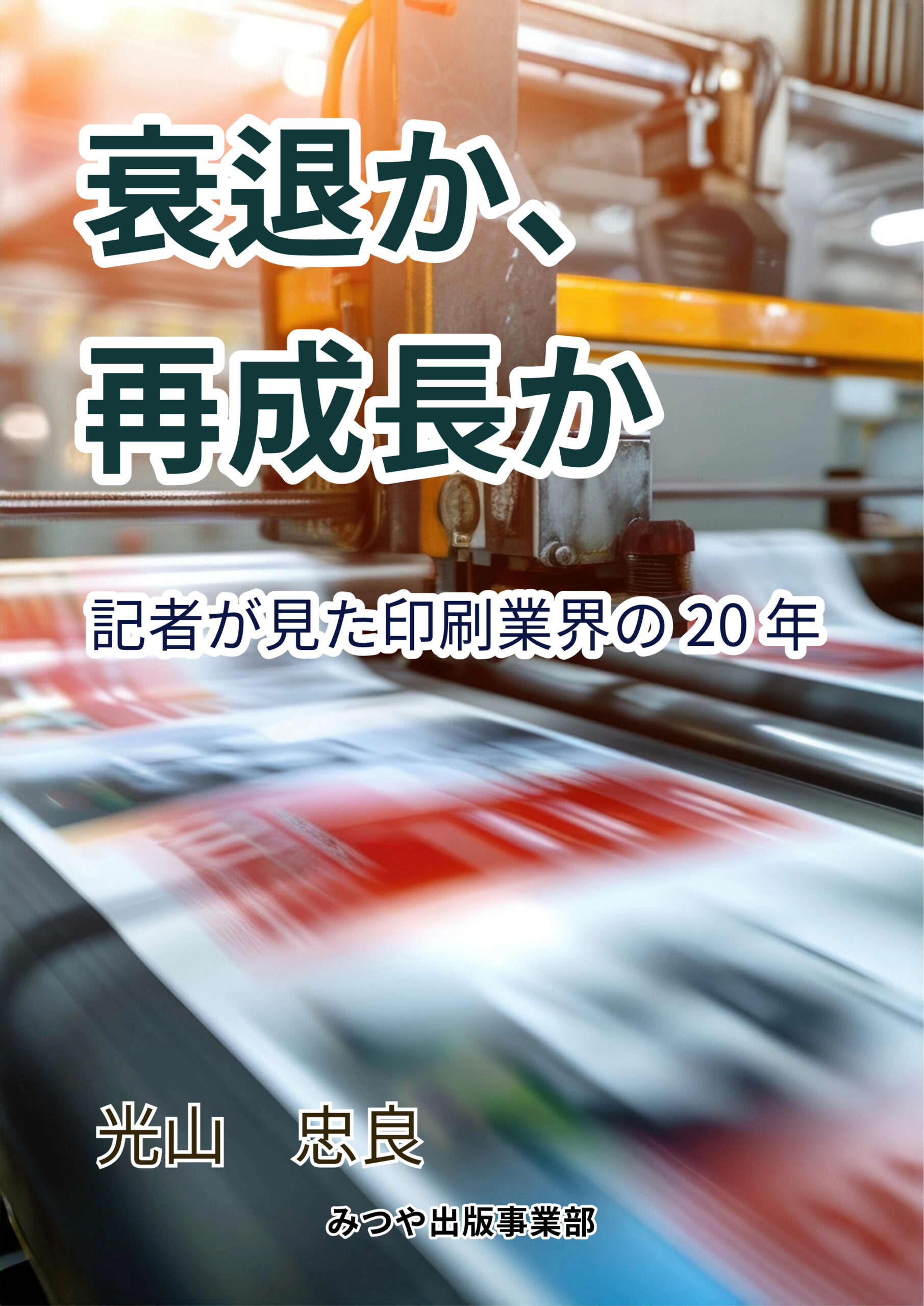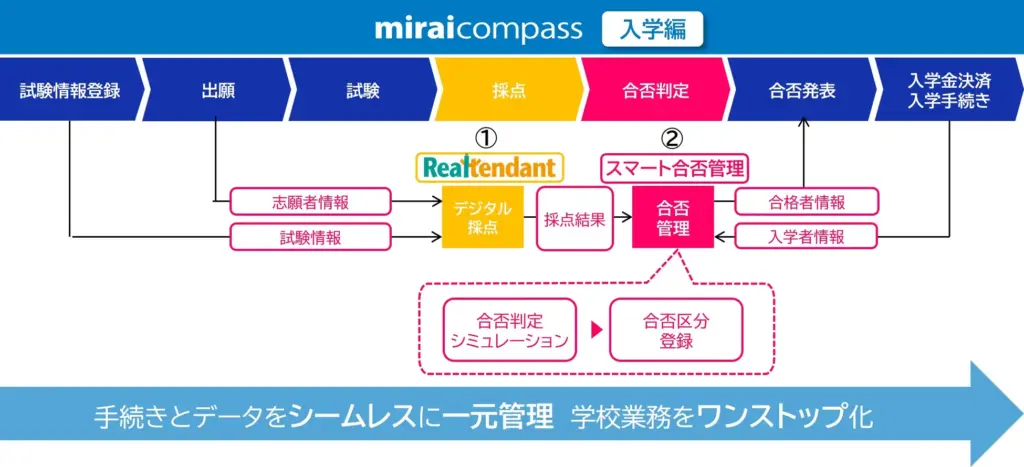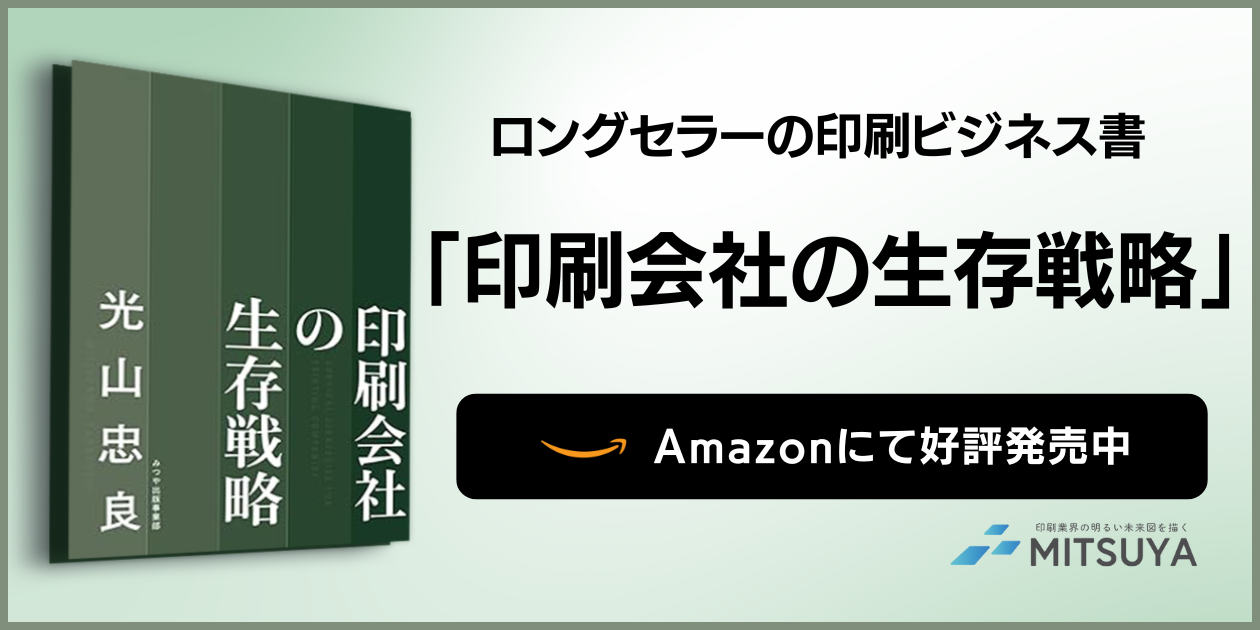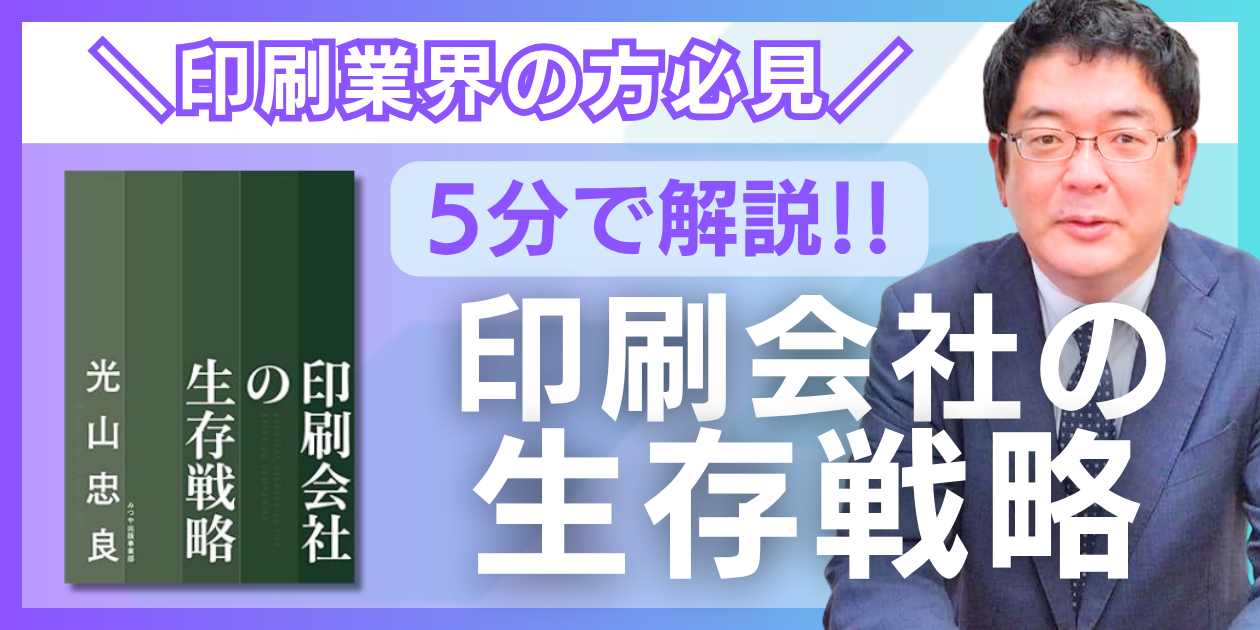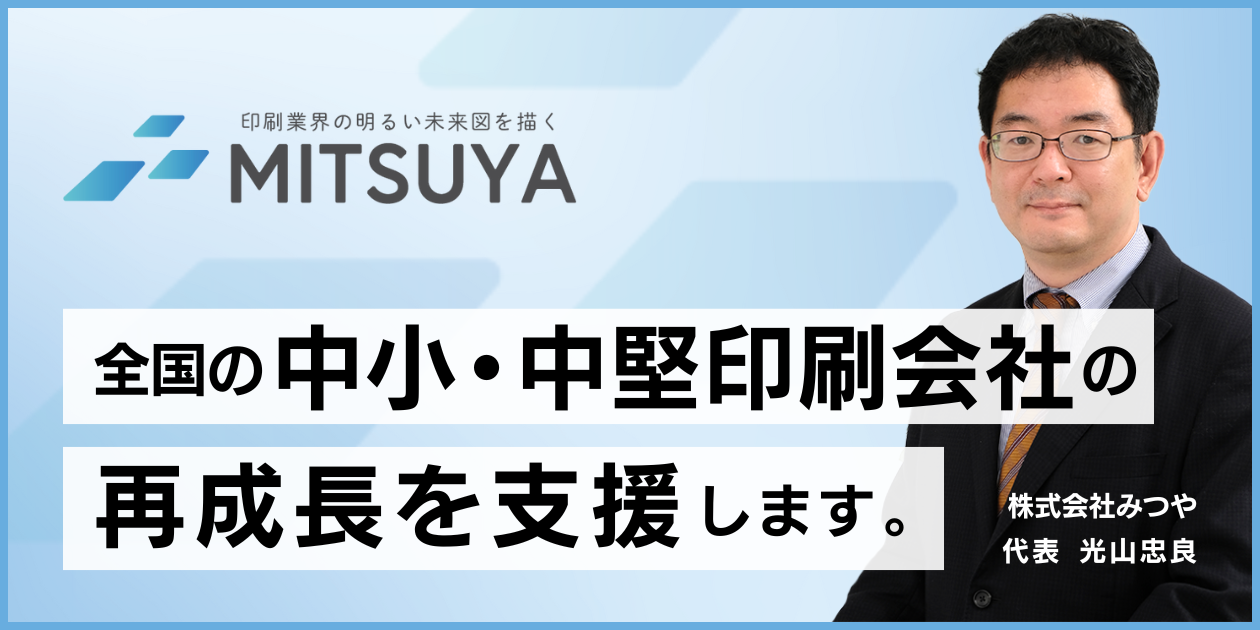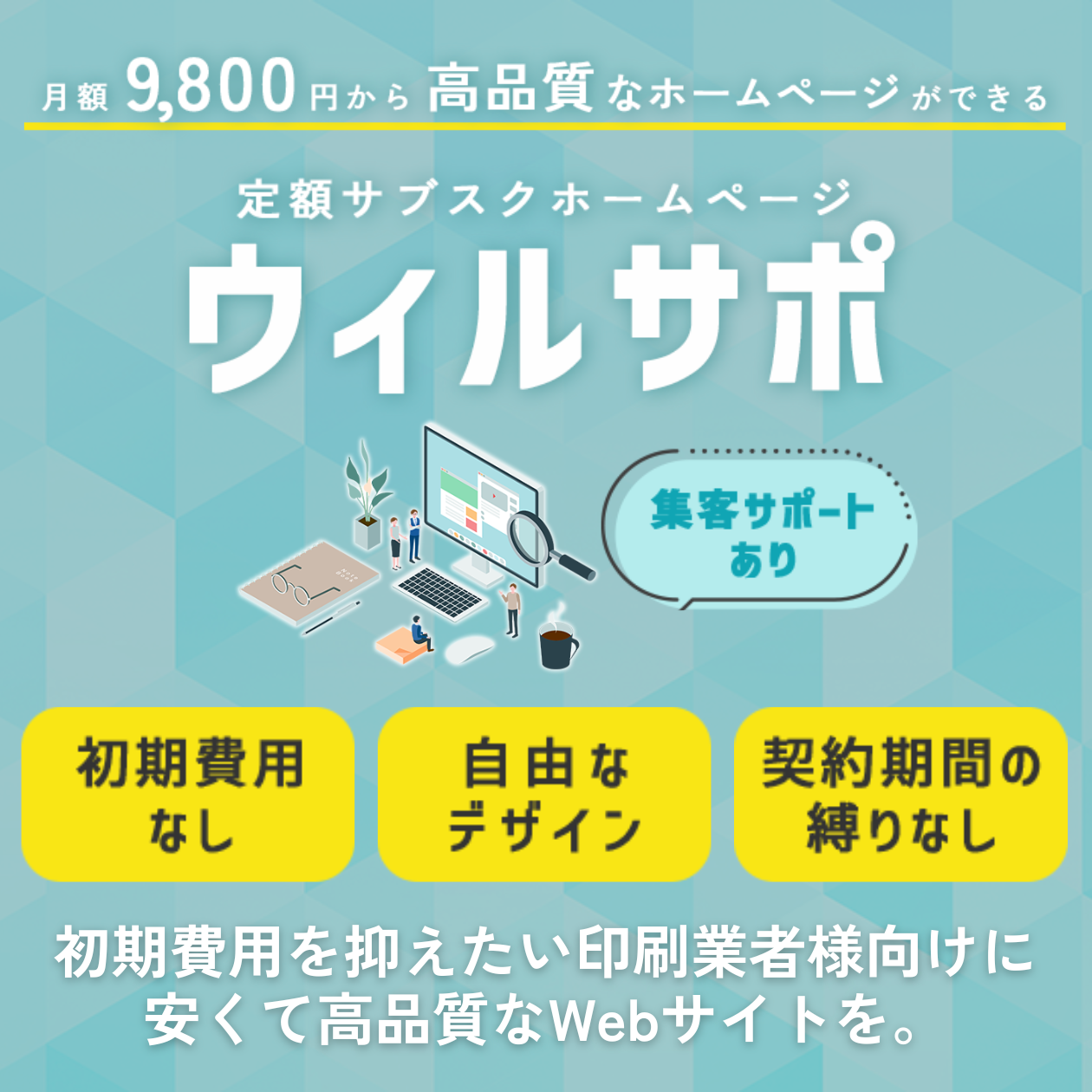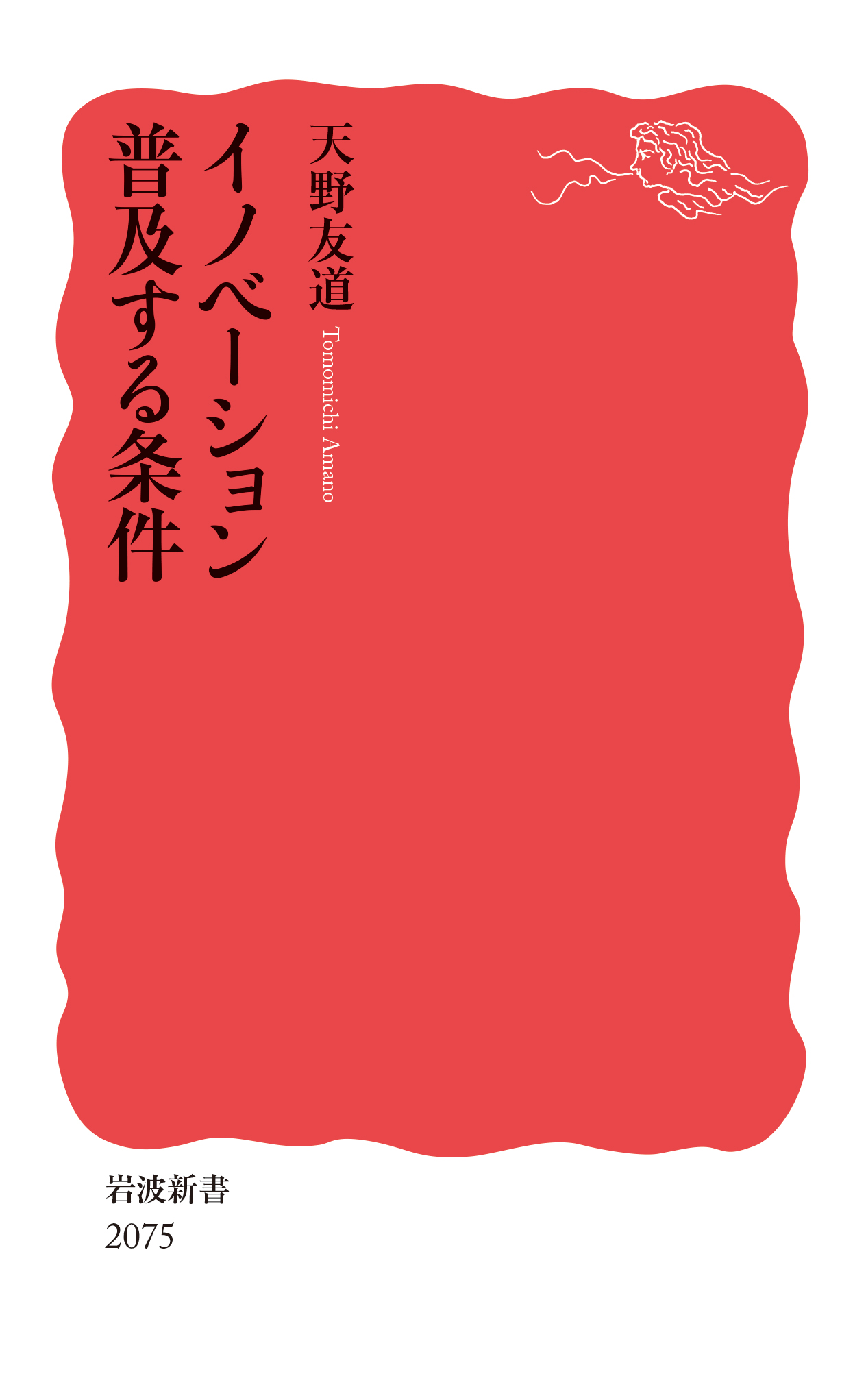
製品には「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」というフェーズがあるという「製品ライフサイクル仮説」は、実に1950年から70年以上にわたって支持されている。経営学の入門書にはもちろん出てくるし、ボストン・コンサルティング・グループの有名な「PPM分析」も製品ライフサイクル仮説を前提としたツールである。導入期から普及期にかけて超えるべき「キャズム(崖)」があるとする「キャズム理論」もよく考えたら製品ライフサイクル仮説を前提としている。
先日『医療4.0』という本を読んでいたのだが、医療業界も「製品ライフサイクル」に拠ってみれば衰退期を迎えていると解説してあった。「製品」を「業界」に当てはめるのはさすがに無理があるのではないかと思うが、ともかく人生のアナロジーとして響くようで、今やマーケティング業界では常識というか、前提とすらなっている。
しかしイノベーションは必ず同様の時間軸に従って普及していくのだろうか、と疑問を呈したのがこの『イノベーション普及する条件』である。その仮説は企業の視点しかなく、消費者の視点が抜けている。
著者は「繰り返し」「おしなべて」使われてはじめてイノベーションであるとし、「繰り返し」「おしなべて」使われない消費者側の事情を「フリクション(摩擦)」と呼ぶ。そしてその要因(例えばチェーン店での商品や店長の力量のばらつき)を除いてはじめてイノベーションが普及すると説く。
とても興味深い指摘である。確かにたとえば活版印刷はヨーロッパでは破壊的なイノベーションとなったが、そもそもの朝鮮半島や中国、日本では長らく普及しなかった。そこには受容する側の背景が抜けていると私も思う。供給側ではなく需要側にたったイノベーションの視点は確かに必要だ。「ブランド」を「繰り返し使用してもらう選択を促すもの」と再定義している点もおそらく『ブランド論』のデイヴィッド・アーカーにもない視点だ。
気になる点といえば、現在のような多様性の時代に、ばらつきをなくす方法がマーケティングといえるのかという問題である。ニッチとか、差別化された製品はイノベーションとはいえないのか。もう一つは、論拠となっているロジャースの『イノベーションの普及』についての解説がほぼないことである。さっそく同著を図書館で取り寄せてみたので、機会があれば評したい。