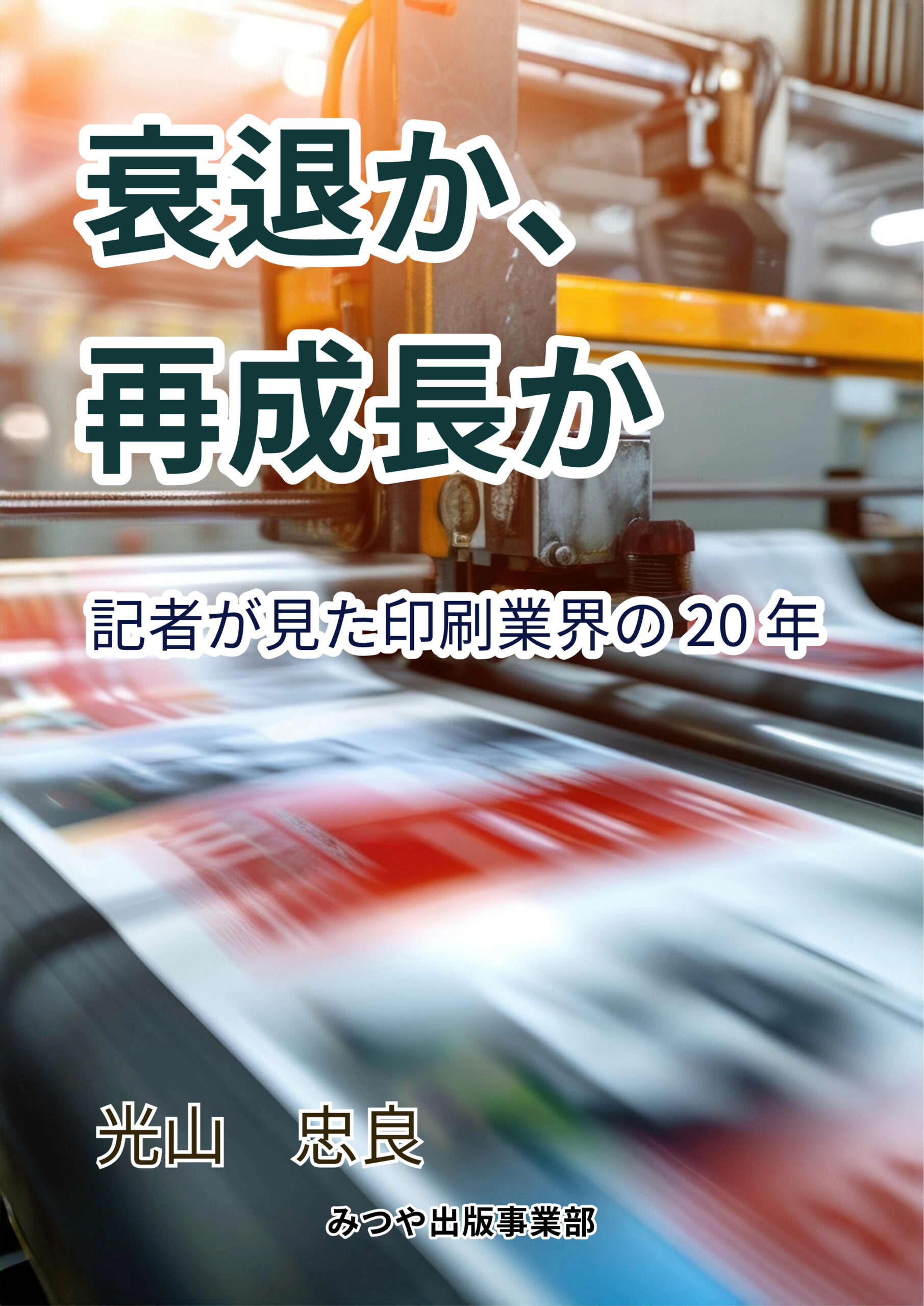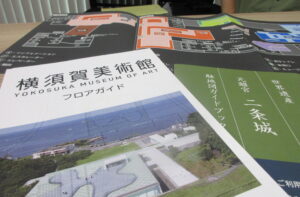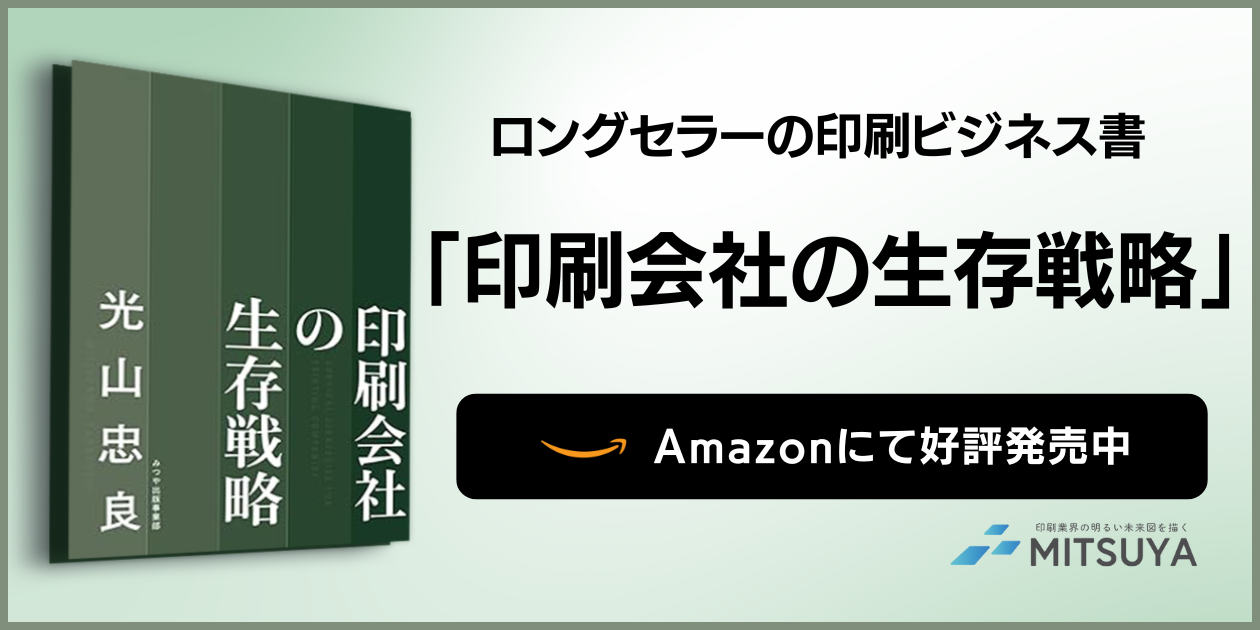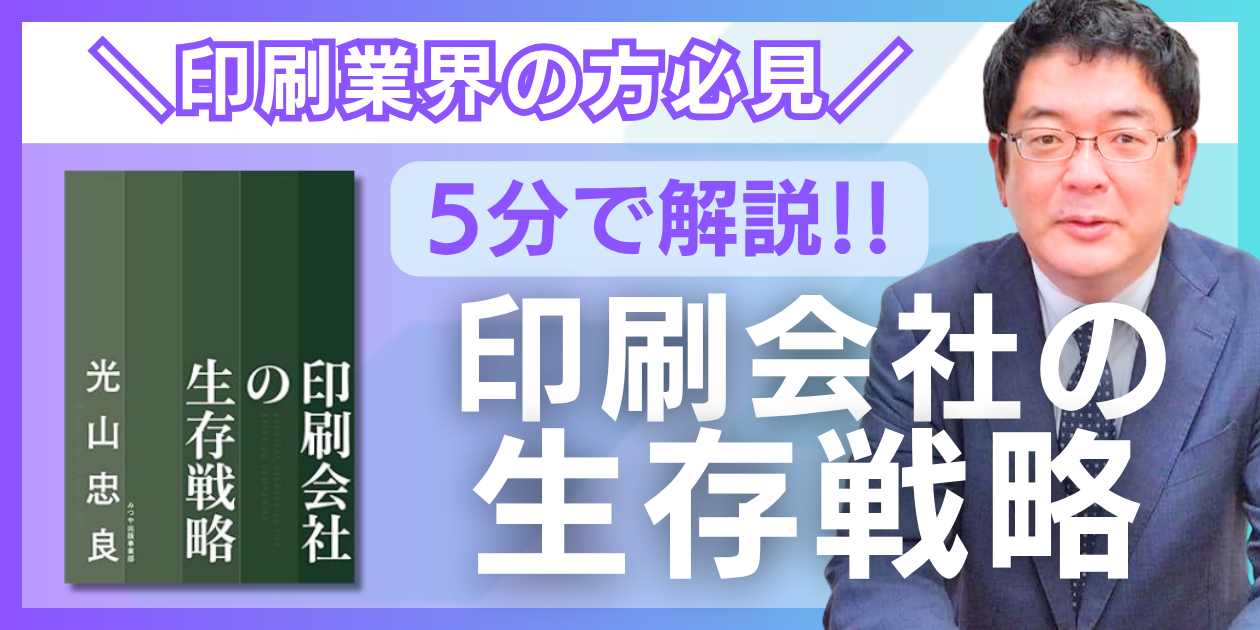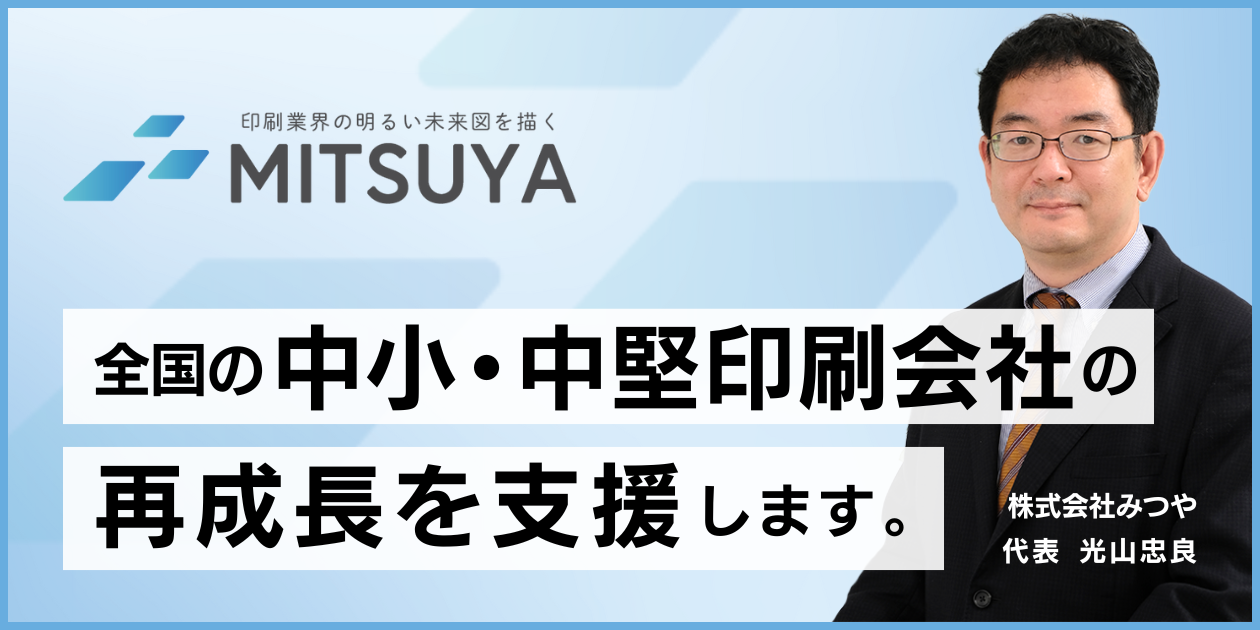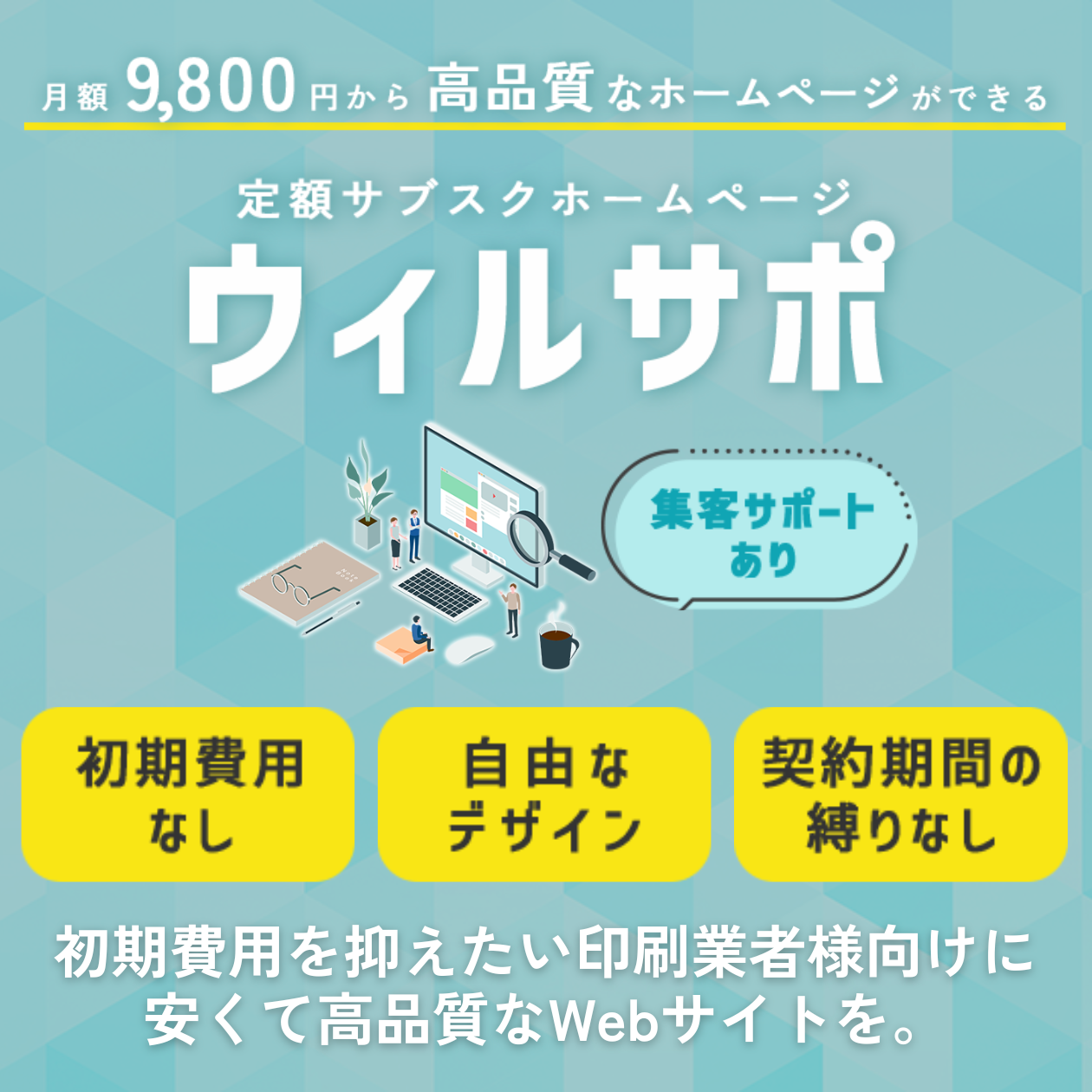株式会社文星閣(東京・大田区昭和島)の代表取締役副社長に2025年2月、奥武士氏が就任した。2021年に入社し、最高戦略責任者(CSO)としてDX化を推進する奥副社長の経歴や展望を聞いた。

――奥副社長のご経歴から伺います。
奥副社長 1994年生まれの31歳です。学歴としては紆余曲折していて、私立中高一貫校を中退して公立校に編入したり、大学も中退してカルフォルニアのコミュニティカレッジに留学したり、そこから勉強してUCLAに編入したりしました。本気でオアシス(イギリスのロックバンド)のリアム・ギャラガーみたいなロックスターになりたいと思って、バンド活動にも夢中になっていました。UCLAでは第2専攻で音楽ビジネスを専攻しました。日本に帰国した後は、ベンチャー企業やベンチャーキャピタルで働き、起業したいなと思っていました。
――文星閣に戻られた(入社された)きっかけは。
奥副社長 コロナで景況が厳しかった2020年に、父(奥継雄社長)に呼ばれ、文星閣を再成長させることができれば経営コンサルタントとしても一人前になれるぞ、と誘われました。最初はコンサルタントとして文星閣の経営に参画したのです。
その後、音楽の道も起業の道もどっちつかずだったのは、いずれ会社を経営したいという思いがあったからなのかな、と腑に落ちるところがあって、本気で文星閣の経営に情熱を注ごうと決意し、入社しました。
――入社されて感じたことは。
奥副社長 日本の印刷産業は巨大産業なのに、まったくアップデートされていないなと。組織も年功序列で評価制度も整っておらず、(ビジョンやパーパスなど)目的も共有されていない。戦略といえるものもない。その一方で、印刷に情熱を注ぐ技術者も多く、知識も技術力もものすごくあって、その点は感動しましたね。
――それでCSO(最高戦略責任者)に就かれたのですね。当初取り組まれたことは。
奥副社長 当社は都内に68胴もの印刷機があって、菊全12色両面機もあるため生産力と短納期に強みがある。強みはしっかりあるのに集客の仕組みがないために稼働率がなかなか上がらない。コロナ禍の危機のなか、まず(利益率よりも)稼働率を上げるために(直需よりも)印刷会社様への営業に注力しました。
それからDXに取り組みました。利益を確保するにも、営業を評価するにも、数値管理が必要です。KPコネクト(小森コーポレーションの生産管理システム)を導入したり、自社開発の「プリントナビゲーター」を構築したりといろいろしました。不必要な会議などが劇的に減ったりして、「別の会社」になりましたね。
――「プリントナビゲーター」開発経緯を教えてください。
奥副社長 伝統的な産業、例えばタクシー業界にはウーバーが、印刷業界でもラクスルなどがITを導入して、劇的にビジネスを成功させています。当社でもDX化に取り組むべきだと当初から考えていました。ところが当社には案件管理もできないようなシステムしかないなど、大きくDX化が遅れていました。
まずはお客様との(見積や受発注などの)やり取りを電話や移動手段を使ったりしないでできる(クラウド受発注インターフェイスの)「プリントナビゲーターバージョン1.0」を自社開発しました。まだまだ自社のためのシステムにすぎませんが、「印刷会社が作った印刷会社のためのツール」として、協業先にも活用していただけるよう、バージョンアップさせる予定です。

――外販されるのですか。
奥副社長 協力会社様には無料でご提供します。
営業のあらゆる活動がウェブ上でできるようにご支援していきたいと考えています。今は見積を書ける若手営業パーソンが少なくなっていると聞いています。セールスフォースと連携させたり、コールセンターを作って連動させたりと、いろいろな構想を練っています。
――今後、営業パーソンが足で印刷物の仕事を取ってくる時代ではなくなるかもしれませんね。
奥副社長 プリントナビゲーターがほとんどの営業活動をしてくれる。当社の営業パーソンはプリントナビゲーターの導入支援に回る――という構想です。
――最後に最高戦略責任者として今後の展望を伺います。ファブレス化が進むと御社のような東京都内に生産力のある印刷工場はビジネスチャンスだと思うのですが。
奥副社長 当社だけが残っていくのではなくて、みんなで頑張っていきたいですね。みなさん得意技をお持ちの印刷会社ばかりではないですか。コラボレーションを促進していきたいです。当社は印刷会社のお客様が多いので、「文星閣コミュニティ」を作りたいですね。コミュニティに入っていただければ、ITやDXのご支援もさせていただけるような経済圏を作っていきたいです。