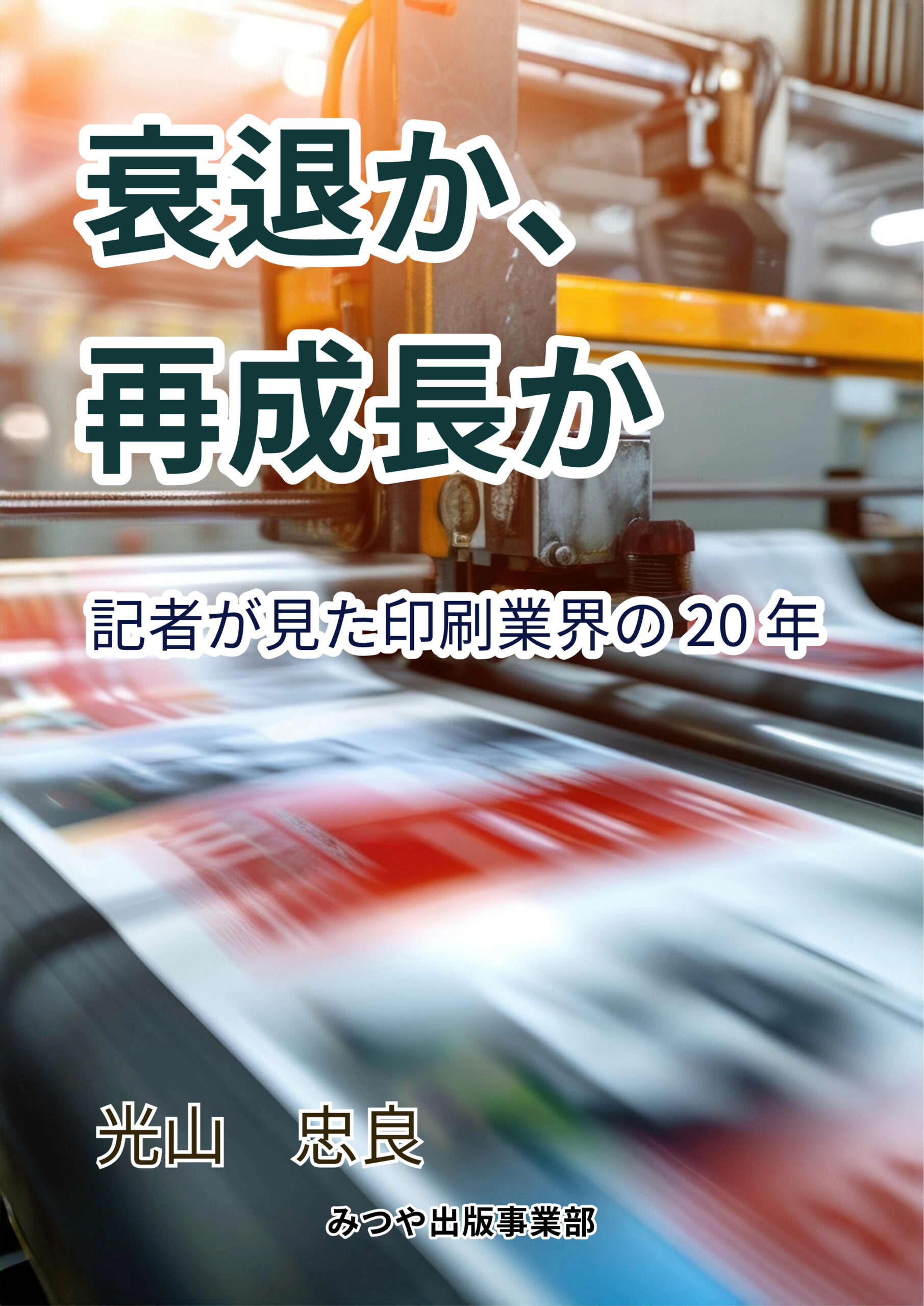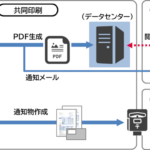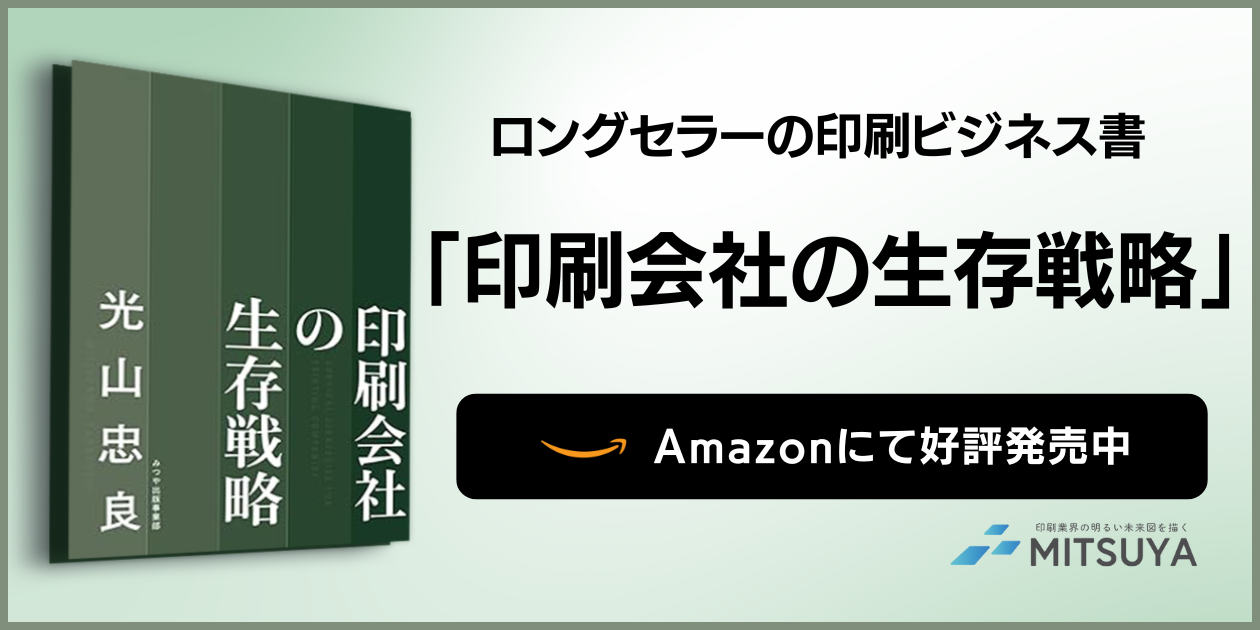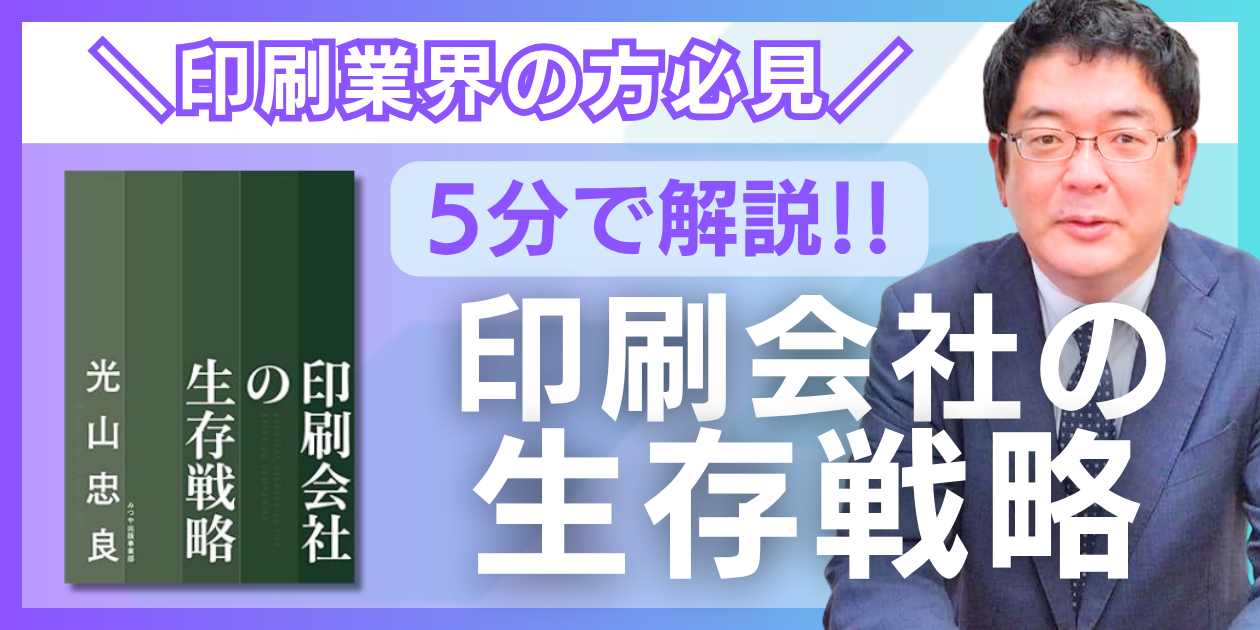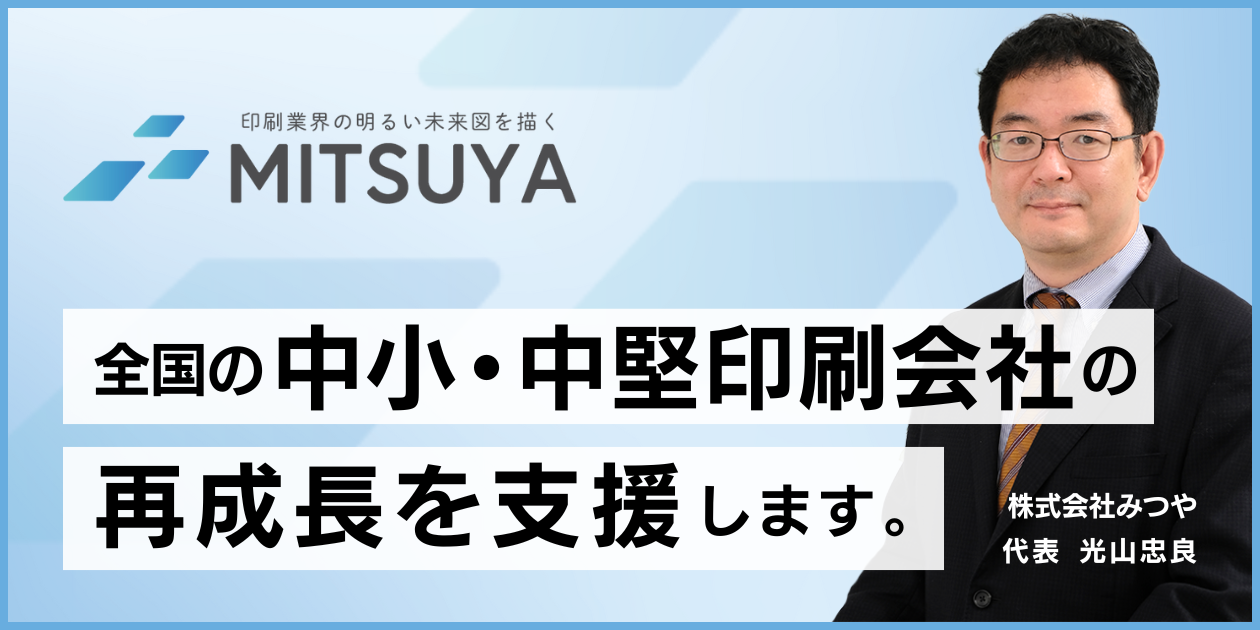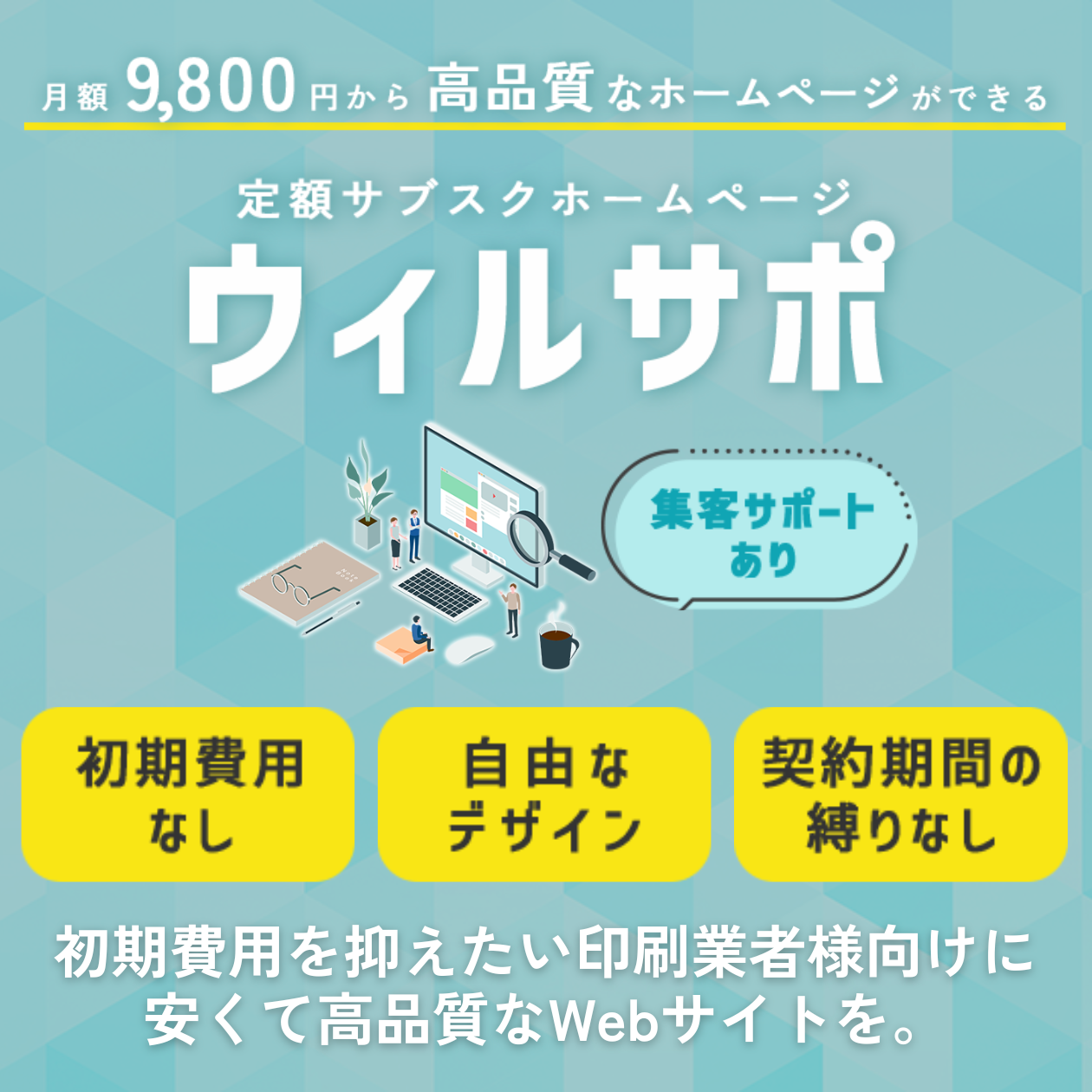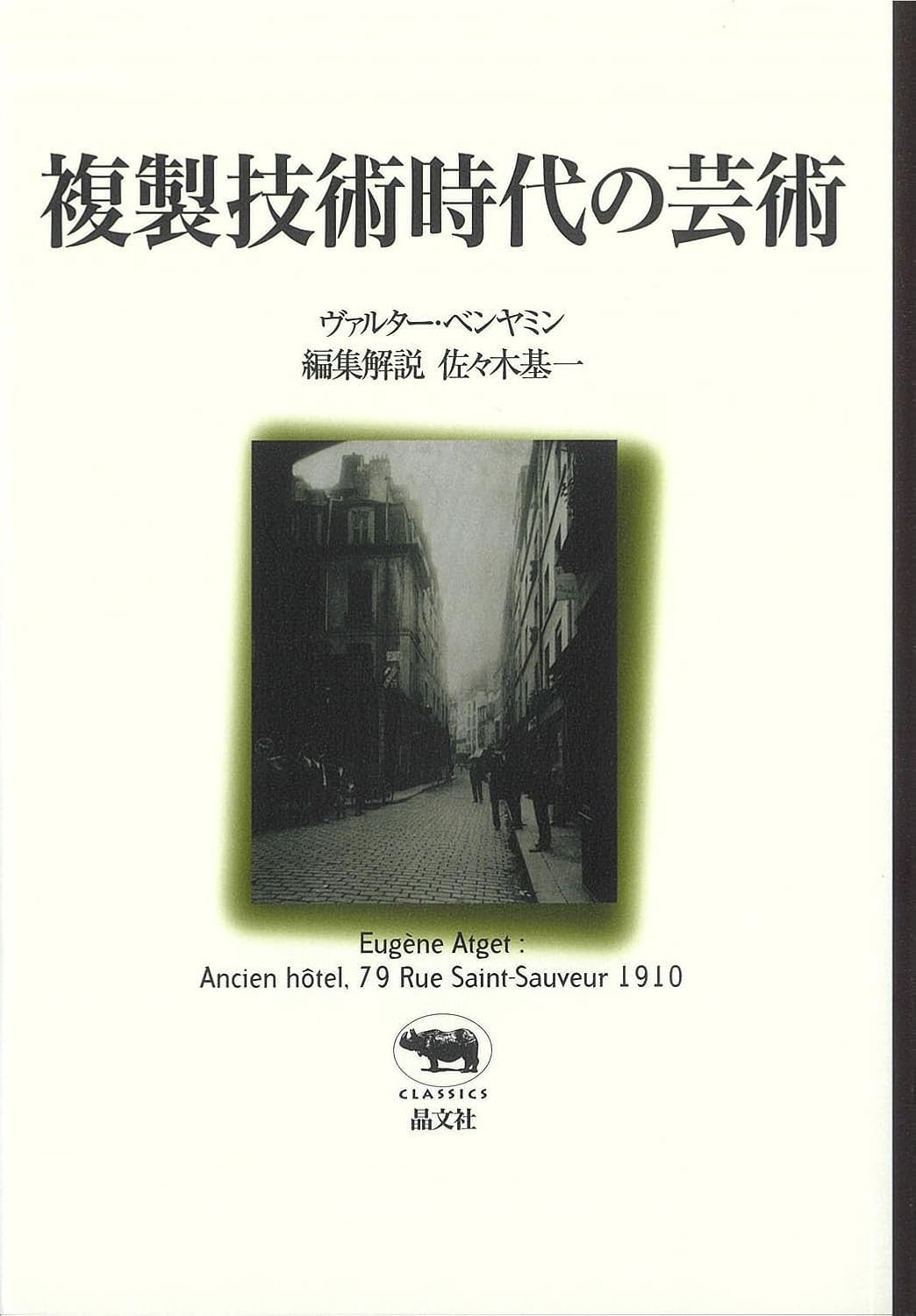
哲学音痴の私がヴァルター・ベンヤミン(1892-1940)による芸術論の古典「複製技術時代の芸術」(1936)を解説することに何の意味があるのかと何度も自問したが、やはりメディア論を語るうえで欠かせない論文であるし、40ページ前後の小論文ということもあってなんとか読めたということもあって、印刷業界の立場から紹介したいと思う。
同論の主張は意外にも明快であるし、現代に生きるわれわれにもすんなり受け入れられると思う。すなわち、ギリシャ時代の彫刻は「いま、ここ」にしかない1回性であり、ゆえに同時代人の態度は礼拝的であった。しかし写真、つづいて映画が現れると、作品の1回性が失われ、作品そのもののアウラ(英語でオーラ)が失われ、人々の態度は(美術館や映画館など)展示的になる。ベンヤミンはそれをネガティブにはとらえず、芸術の大衆化への可能性を示唆している。
なおベンヤミンは、19世紀初頭の石版印刷(リトグラフィ)の歴史的価値を高く評価し、グラフィックの大量生産と絵入り新聞という新製品を世に送り出したが、数十年で写真に追い越されたとしている。実は印刷の黄昏はこのころから始まっていたのかもしれない。
さて、ど素人の感想である。「アウラ」は本当に消失したのか。裁判や死の床に際して手を当てるあの聖書は、無宗教家にとっては原価数百円の冊子であっても、クリスチャンにとってはアウラそのものである。大谷翔平選手のプレミアムカードは、無関心な人にとっては水につければ溶ける代物でも、ファンにとってはアウラに包まれた宝物である。数十万部売れたとしても、推しの写真集は推しである限りアウラでありつづけるだろう。
「いま、ここ」の1回かぎりなはずのアウラを複製してみせるのが、印刷メディアの(残された)役割なのではないか。無限に複製できるデジタルコンテンツではなく、それを1回限りに押し込めようとするブロックチェーン絵画でもなく、プロンプトとアルゴリズムで1回限りのオリジナル画像が生成できる生成AIでもなく、他でもない印刷物こそが、アウラを担保しうるのではないかと思うのである。
すごくかみ砕いていうと、ファン垂涎ものの写真集、DVDジャケット、フィギュア、トレーディングカードを作りましょうということである。たぶん新聞やチラシなども紙メディアは減少しつづける。「いま、ここ」しかない複製物を作るという一見矛盾したグラフィックアーツに、印刷産業の隘路が見える気がしてならない。