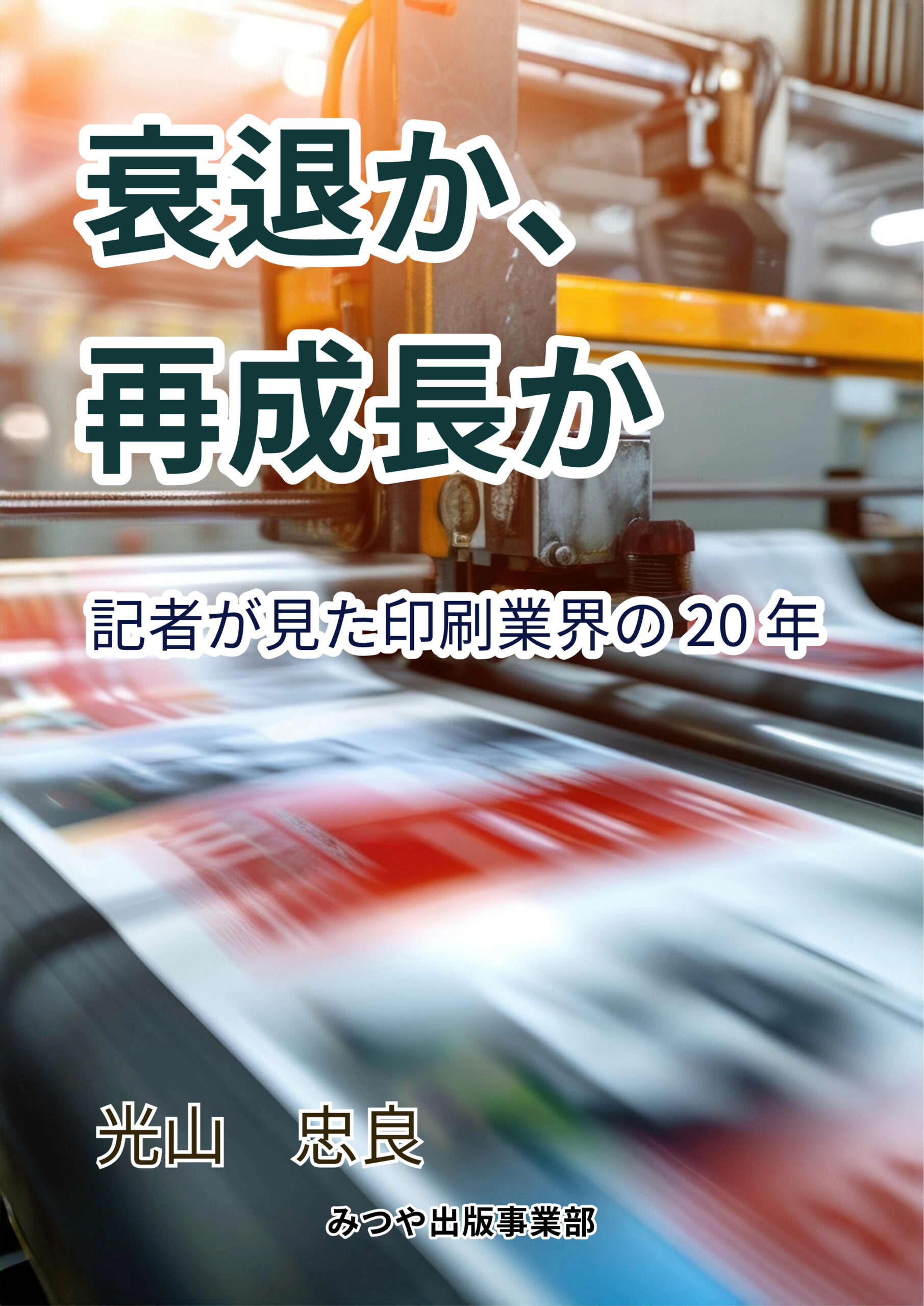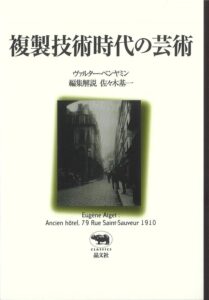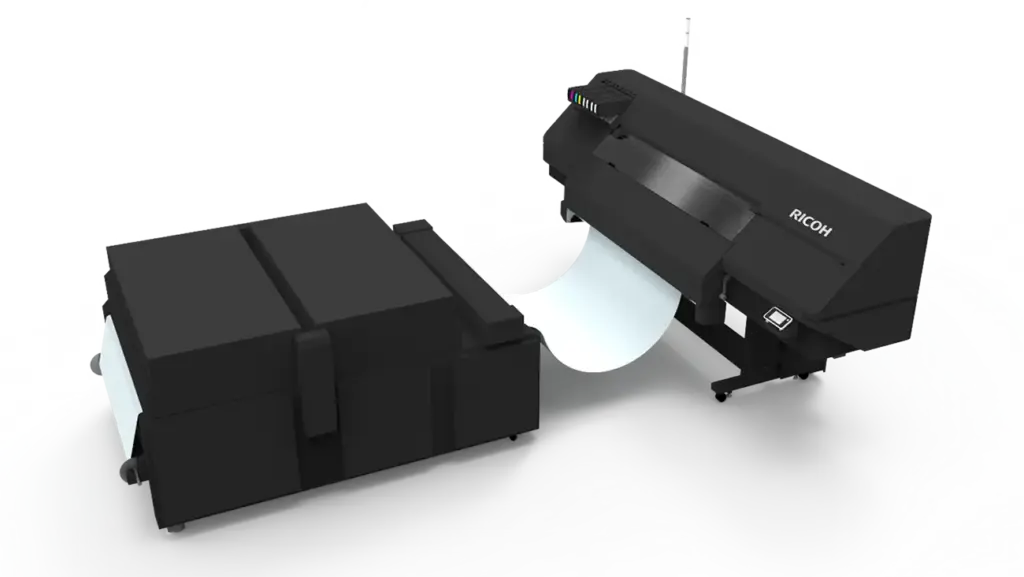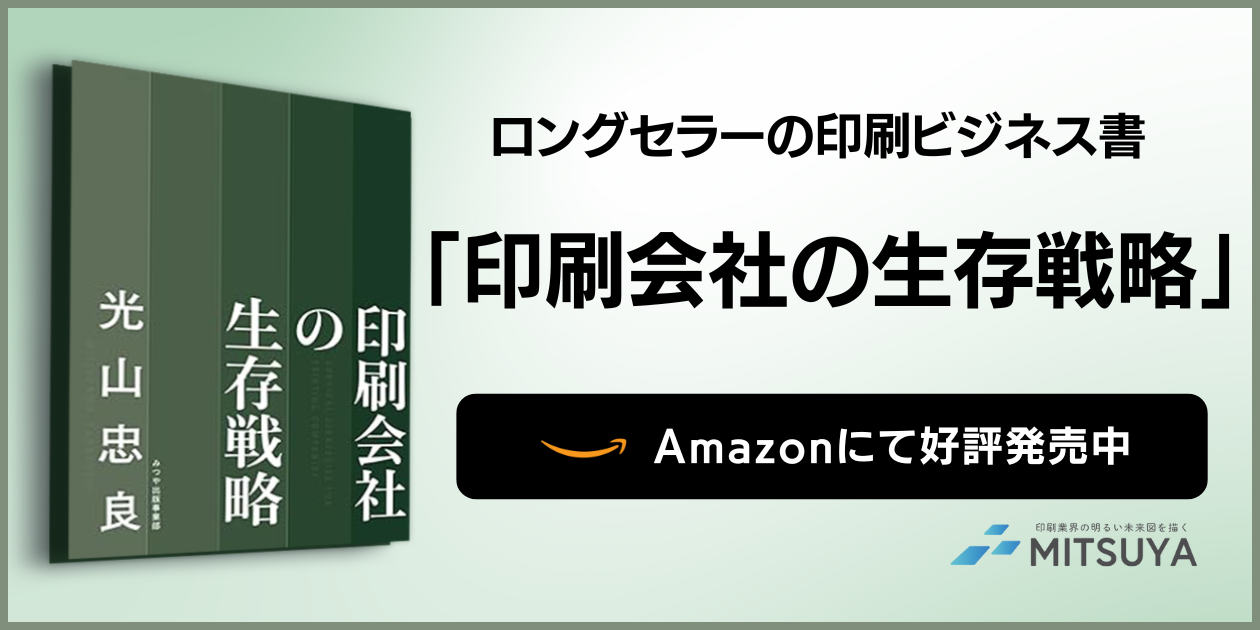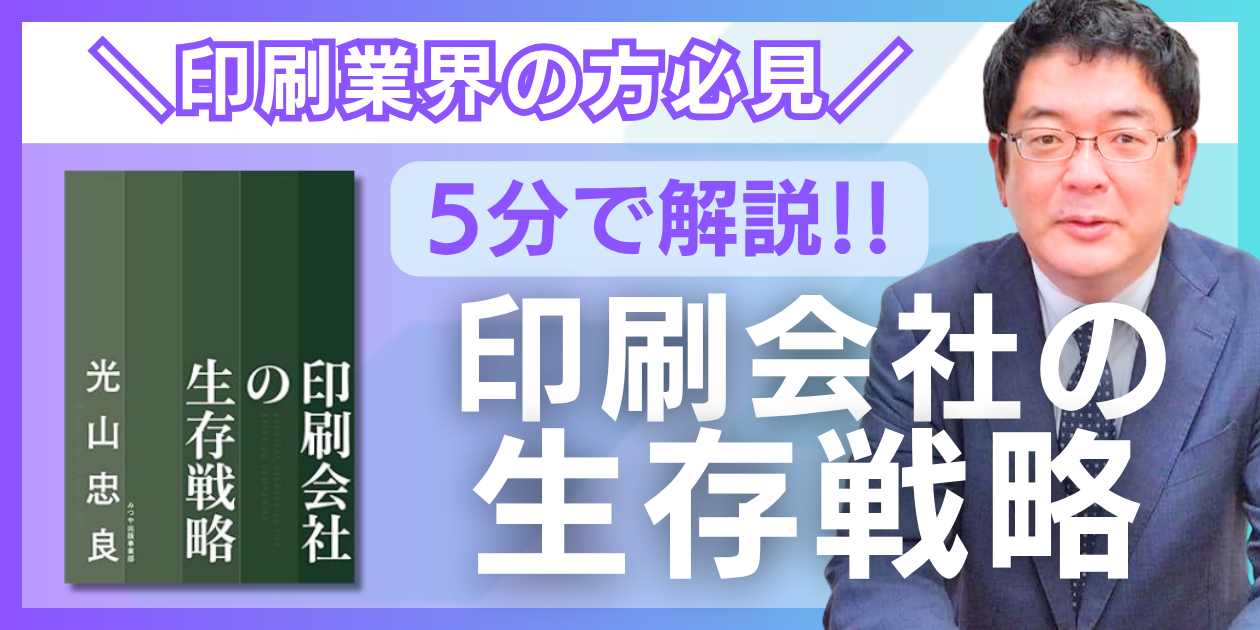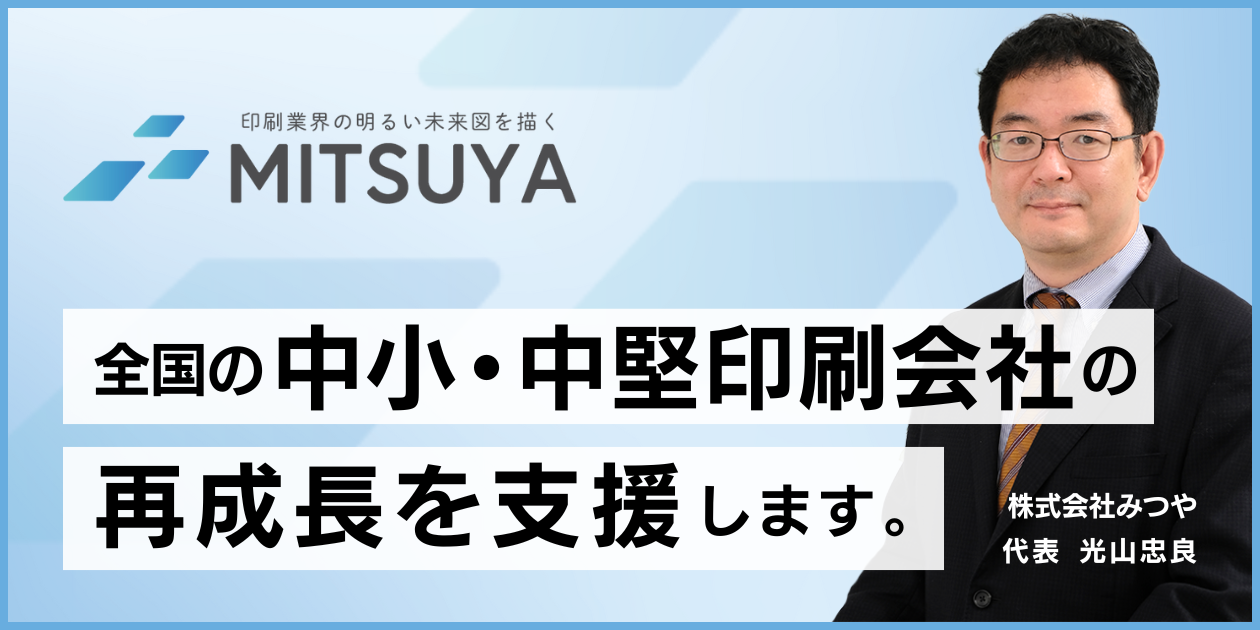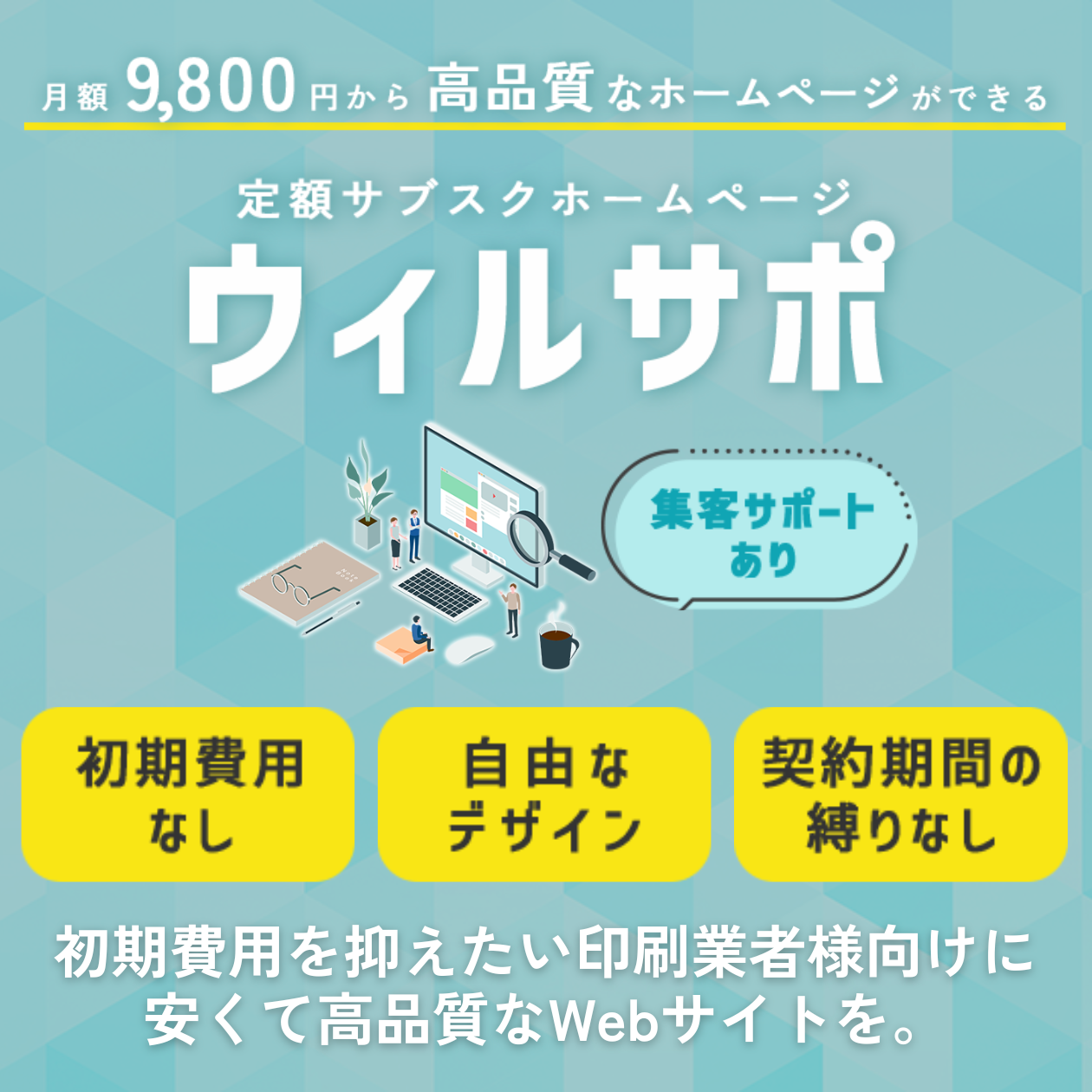デンマークとスウェーデンの郵便事業体・ポストノルドが2025年末をもってデンマークにおける手紙の配達を廃止すると発表し、日本の印刷業界でも話題になっている。ヨーロッパでは電子化が進んでいるとか、時代の趨勢でいずれ日本もそうなるとか、そもそも郵便ポストが1500基しかない脆弱なインフラが郵便事業を悪化させたのだとか、公的通知が届かなくなることはありえないとか、様々な議論が寄せられているので、いったん整理したいと思う。
まずヨーロッパと一口にいっても、郵便業務発展総合指数1位のスイスと、いつまでたっても手紙が届かない58位のポルトガルを十把ひとからげにされても困る。そこで同56位のデンマークの特殊事情について整理してみよう。
福祉国家として知名度が高いデンマークだが、2001年に「デンマークの小泉純一郎」とも評されたラスムセンが首相に就いて以降、「世界一の電子政府」を掲げ、郵便事業の構造改革に取り組んできた。そして2015年以降は原則、公的機関とのやり取りはすべての住民が持つ「電子私書箱」を利用しなければならないとされた。
その結果公的機関から個人あてに送付される郵便物は基本的に廃止され、郵便物は激減の一途をたどる。人員は削減され週1回しか郵便物を受け取れなくなった。郵便ポストは遺棄され、落書きだらけの郵便ポストが目立つようになった。郵便業務発展総合指数は先進国平均の67.40を大きく下回る48.48(56位)となった。デンマークでは21世紀はじめから手紙の量が14億通から1億1000通へと90%減少しているが、これはヨーロッパでも際立った減少率であり一般化はできない。
論点の二つめは、デンマークにおける手紙の配達がなくなったわけではないということである。デンマークでは2011年から郵便市場が完全自由化になり、ポストノルド以外の民間事業体が手紙の配達を継続する。トマス・デニエルセン運輸相は「手紙や小包については自由市場が存在する」ため、手紙を出したり受け取ったりすることは引き続き可能だと述べ、国民に理解を求めている。
論点の三つ目は、ポストノルドの経営戦略である。インターネット、とくにEメールとネット通販の進展により、手紙が減って小包は増えるのは時代の趨勢であり、ポストノルドが手紙ではなく小包するのは当然の経営判断だろう。
さて、日本の印刷業の話に移る。2024年10月の郵便料金の値上げにより、DM・請求書・年賀状市場は大打撃をこうむった。郵便業務発展総合指数3位の日本においても、郵便局がインフラを維持できるかどうかはわからない。
「手紙から小包へ」の時代に勝つには、包装資材の製造にシフトするか、小包に同封する販促物に注力するか、ということになるだろう。前者の商業印刷からパッケージ印刷へのシフトは非常に参入障壁は高いが挑戦すべき市場だろう。そしてAmazonに独占されている感のあるネット通販であるが、D2C、すなわち直接消費者へと届けるネット通販事業者と提携して、同梱の販促物をまとめて受託するというビジネスも挑戦しうる。
手紙へのノスタルジーに浸る余裕はない。時代の趨勢にしたがって、ビジネスを変える努力が必要だと考える。