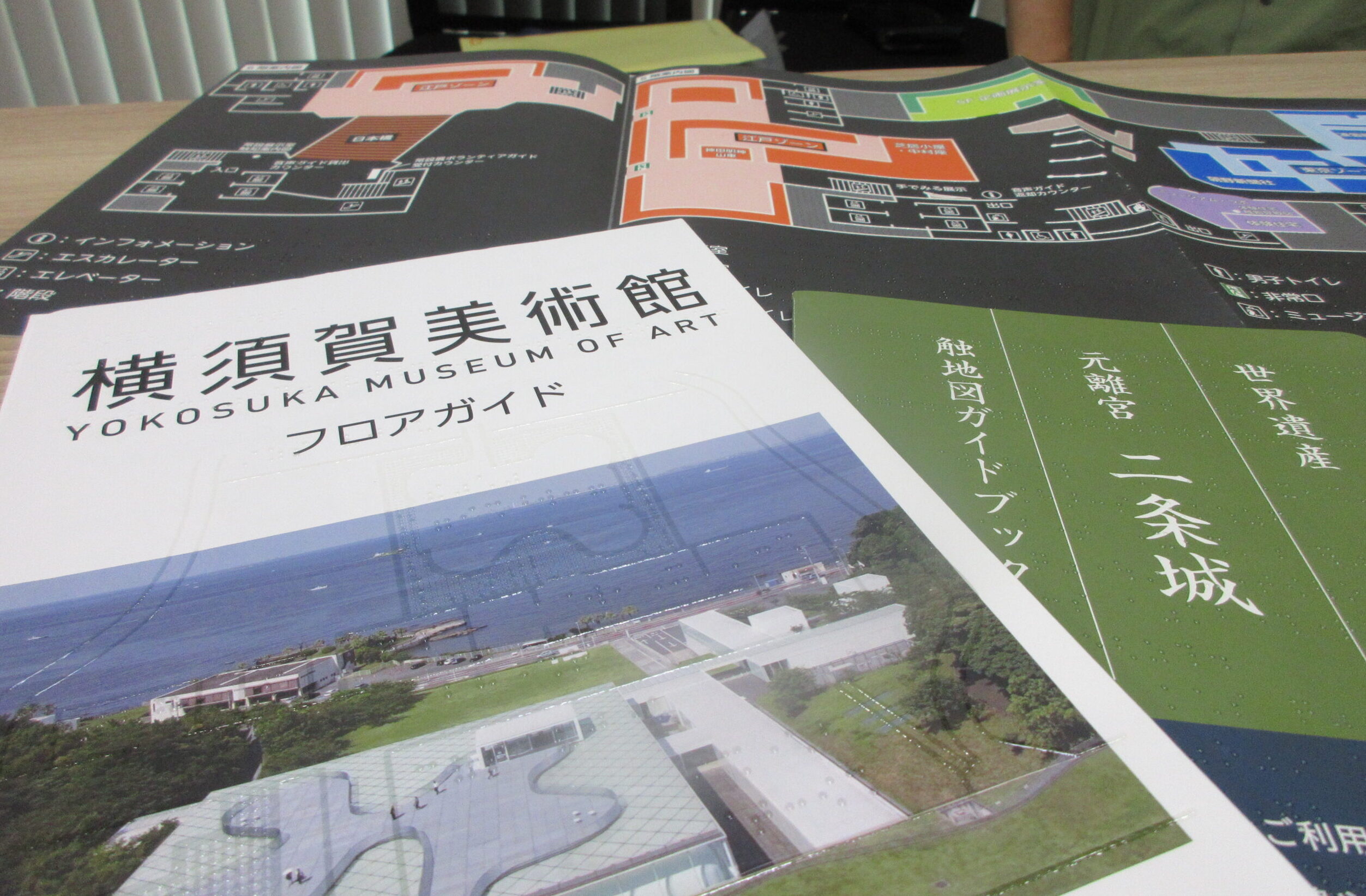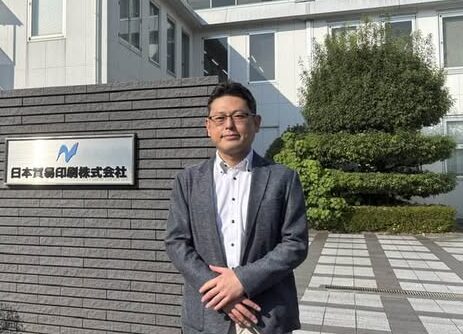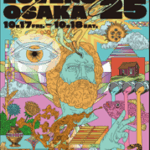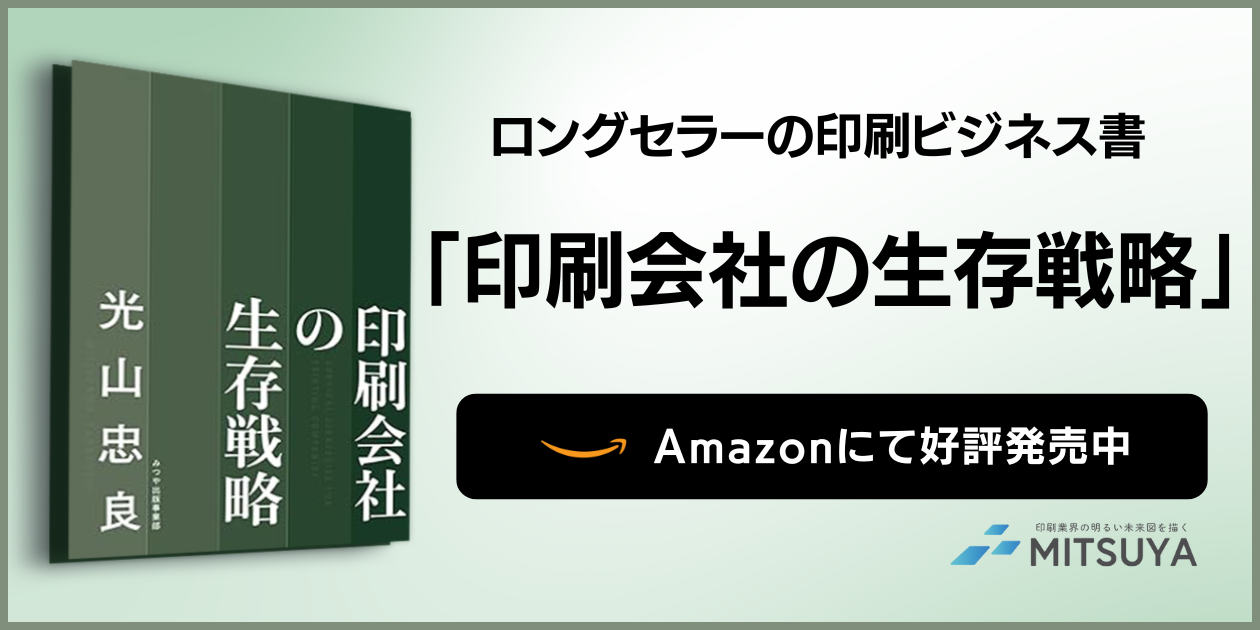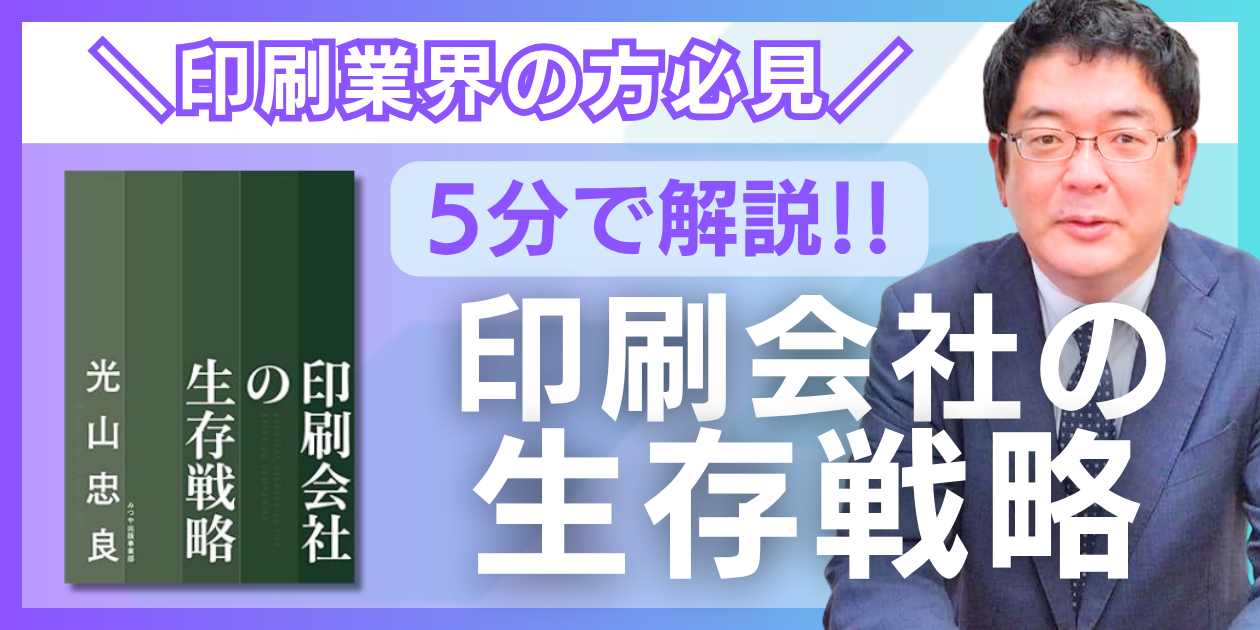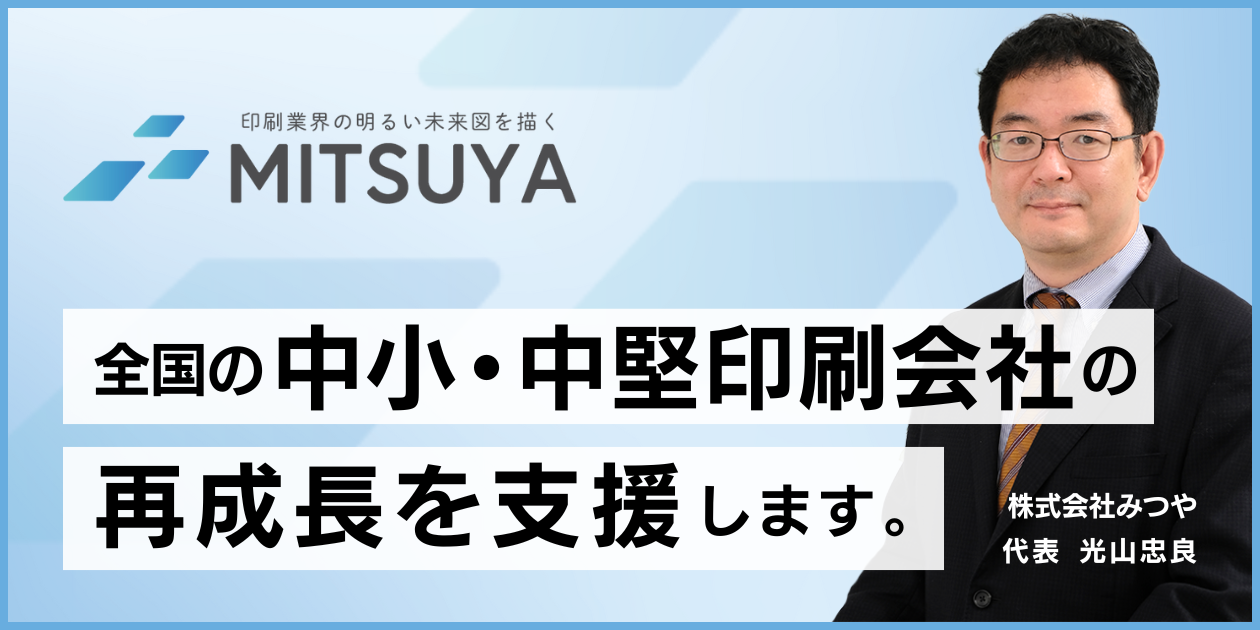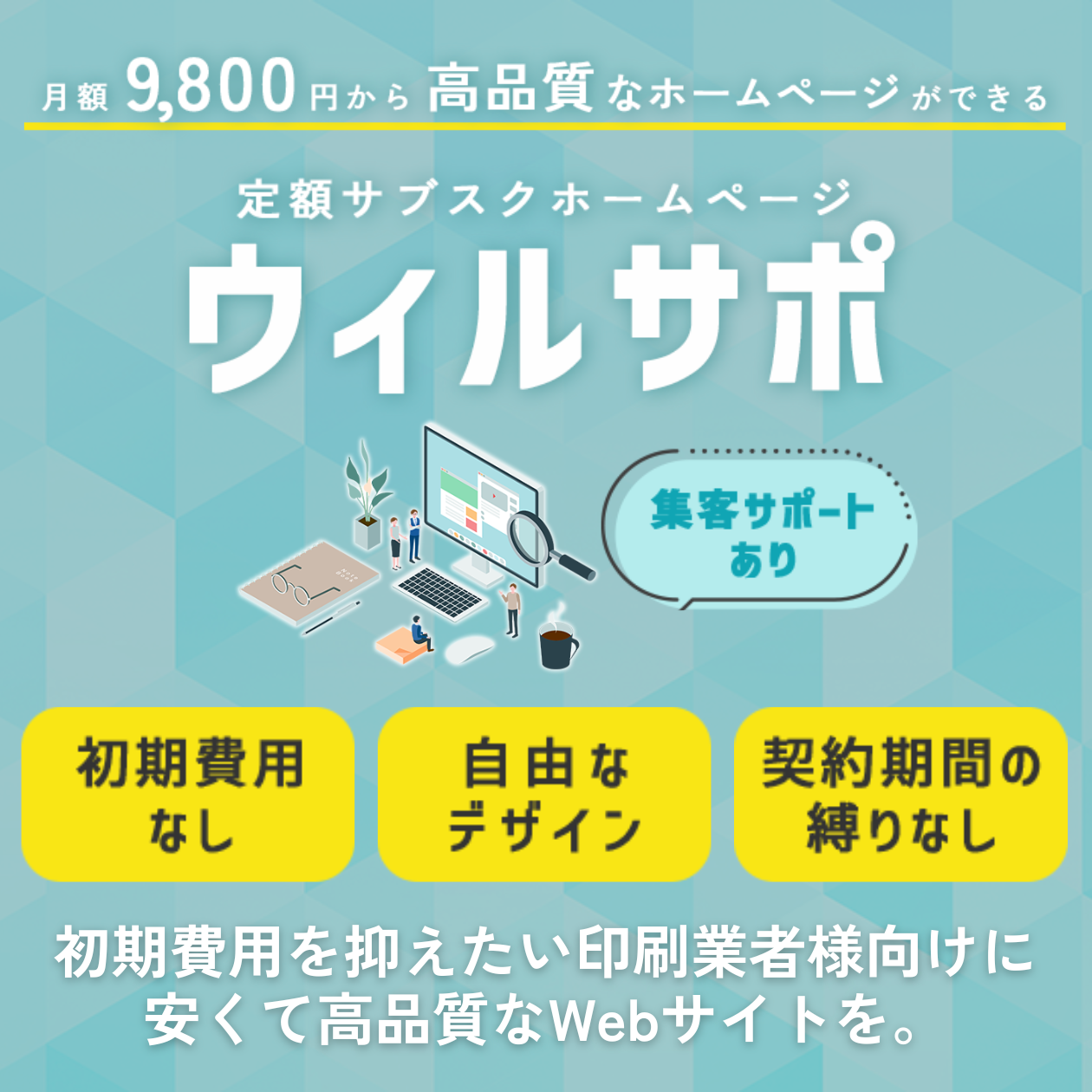履修要綱や卒業証書など大学向け印刷物の提供で知られる株式会社コームラ(岐阜市、鴻村健司社長)は、ドキュメントの電子化や少子化の進展を見通し、大学の先生が実行委員長を務める学会大会の事務局運営代行サービスを2013年から開始、年間200大会運営の実績をあげている。11台のデジタル印刷機でフルデジタル化し、DXにも取り組んでいる同社を訪問し、事務局運営(BPO)と印刷物製造(PSP)の相乗効果を探った。
大学と先生にワンストップサービスを提供
株式会社コームラは1937年に創業、戦後に中央官庁や国の出先機関、国立病院、国立大学等に共通書式印刷物をカタログ通販するビジネスで成長した。デジタル化、入札による価格下落、官公庁の再編などで官公需が低迷すると、国立大学で培った信頼とノウハウを私立大学に広げ、主な顧客を大学とした。現在は北海道から沖縄県まで約130校にホームページのほか、大学案内、シラバス、卒業証書などあらゆる印刷物を提供している。
少子化や紙のデジタル化などを踏まえて、同社の成長エンジンとしてとらえているのが、学会大会の事務局運営代行である。学会大会は大学の先生が実行委員長になって開催されるが、アカデミックな世界にいる先生は、チラシやポスターの発注や会場設営などの煩雑な作業を得意とはしていない。そういった先生に替わって事務局の業務全般をワンストップで代行するのが同社の事務局運営代行サービス「学会スマート」である。学会の抄録集の製作をきっかけにスタートした「学会スマート」は、現在ではWeb申込受付システムによる参加者募集、参加証やポスター、プログラム、看板、案内板などの製作、大会・懇親会会場の設営、事務局員の配置など実に多岐な業務を行う。
今でこそ学会運営を代行する印刷会社は全国に存在するが、2013年に中小規模の学会運営の市場に注目した同社はパイオニア的存在である。コロナ禍でもZOOMによる運営で切り抜け、むしろZOOMとリアルのハイブリッドな運営ノウハウも修得した。現在は年間約200大会の事務局代行をこなす。
大会委員長である先生との横のつながりや紹介のほか、意外にもネットでの問い合わせも月10本のペースで寄せられる。全国の先生と打ち合わせをするために、フェイス・トゥ・フェイスのほかZOOM会議なども活用する。そのため同社ではマーケティングオートメーション(MA)やホームページのSEOにも力を入れている。
デジタル印刷はDXの肝
印刷会社以外にも事務局運営会社は存在するが、同社の強みについて鴻村社長は「ものづくりができるという点に尽きる」と話す。「WEB制作からドキュメント製作まで自社でできるからなにしろ対応が早い」。
そのドキュメント製作で目に付くのは、なんといってもモノクロ8台、カラー3台の計11台の粉体トナーデジタル印刷機による生産体制である。もともと1997年に岐阜県で初めてデジタル印刷機を導入したが、2019年に富士フイルムの「Iridesse Production Press」の印刷品質を見て、「このクオリティだったらフルデジタルでいける」(鴻村社長)と判断して、3台のオフセット印刷機を全廃し、フルデジタル化に移行した。

「オフセット印刷とハイブリッド環境にすれば損益分岐点は何部だろうと計算したり、かなり研究したが、実際にフルデジタル化にしてみると(オペレーションが)軽くなってよかった」と鴻村社長。
その恩恵は多岐にわたる。インキやウェスなどの諸資材の発注・在庫管理が必要なくなったことで、生産現場だけでなく管理部門においても煩雑さがなくなった。プリプレス部門においてもオフセットとのハイブリッド環境だと面付を都度変えなければならなかったのが一本化できた。オペレーターも女性・男性を問わず採用できた。中でも11台のデジタル印刷機を3人のオペレーターをこなすことができる省人化の効果は大きい。「デジタル印刷はDXの肝。各社の商材や方向性によって異なるかもしれないが、当社はデジタル印刷を推進したい」と話す。
鴻村社長は今後の展望について「900億円市場と言われる学会運営のうち、近い将来に10億円のシェアを取っていきたい。またシンポジウムや公開講座など大学のイベント運営にも力を入れていきたい。そういった(コトづくりの)事業が伸びてくれば、付随して印刷物の受注も増えてくる」と話している。
印刷事業とBPO事業の相乗効果に活路
鴻村社長に大学・学会向け印刷物と事務局運営サービスについて聞いた。あらためて重要と感じるのは印刷事業とBPO(ビジネス代行事業)とのシナジー(相乗効果)である。印刷事業があるから瞬発力のある事務局運営ができる。事務局運営ができるから付随する印刷物の受注も増える。大学・先生という顧客に対し、印刷事業とBPOの両面からアプローチしていく同社に、印刷会社のあるべき未来を感じた。