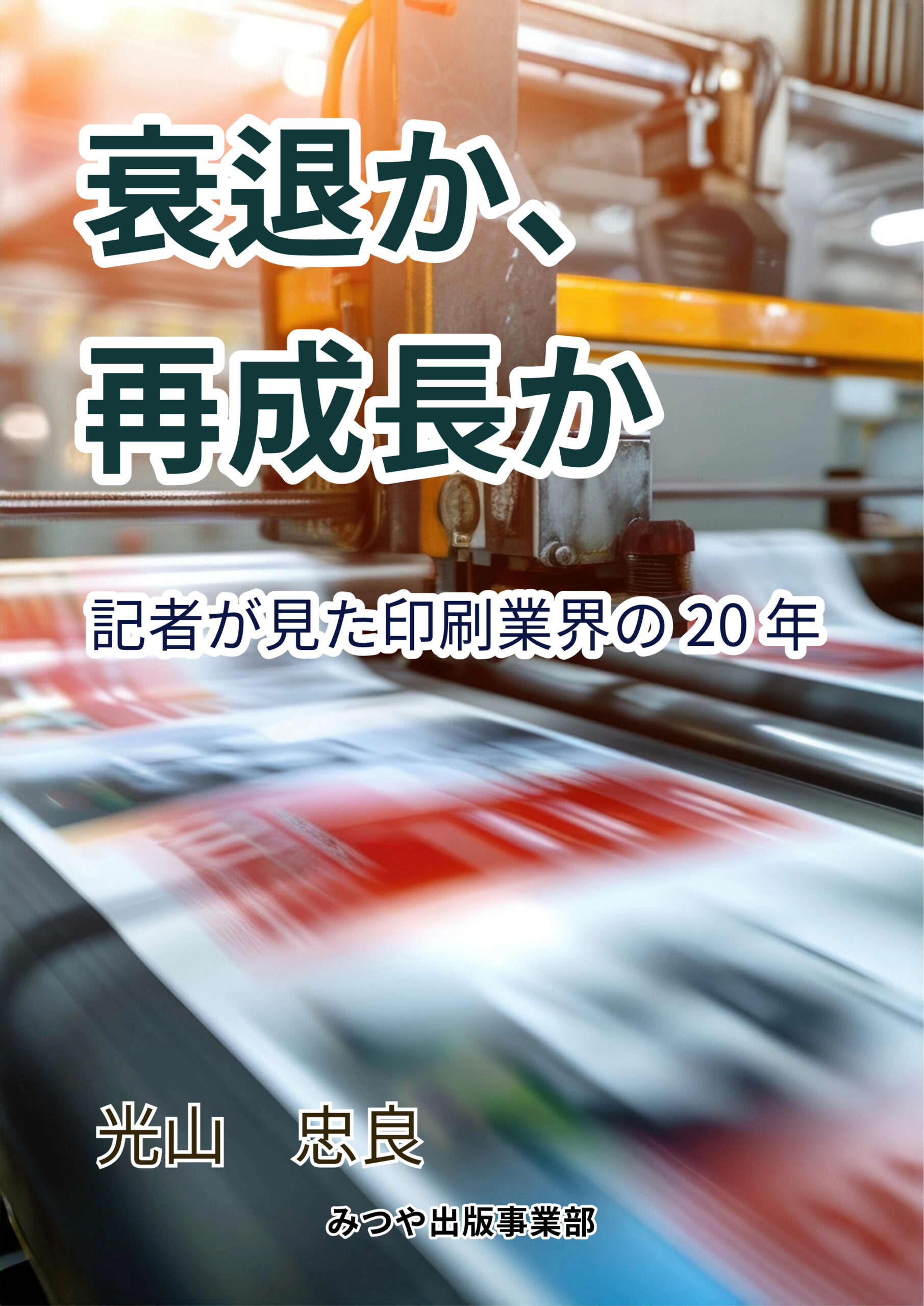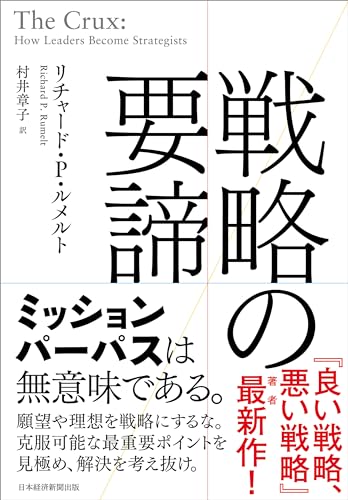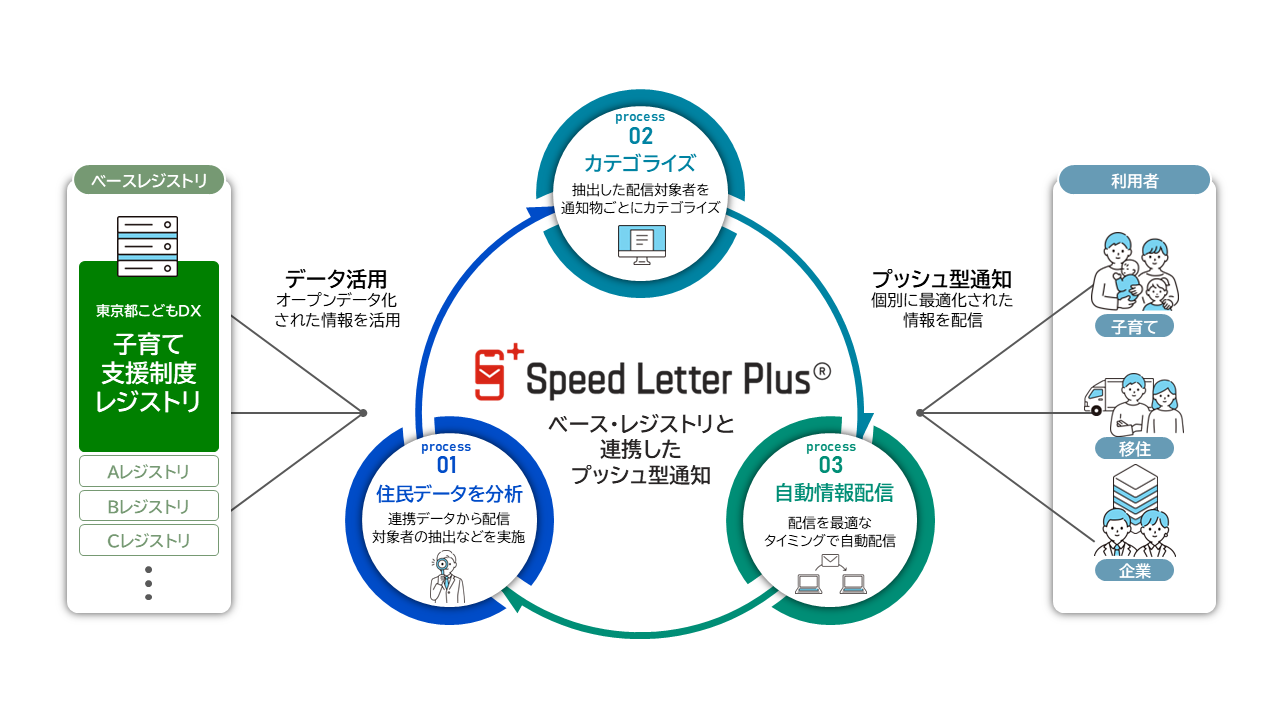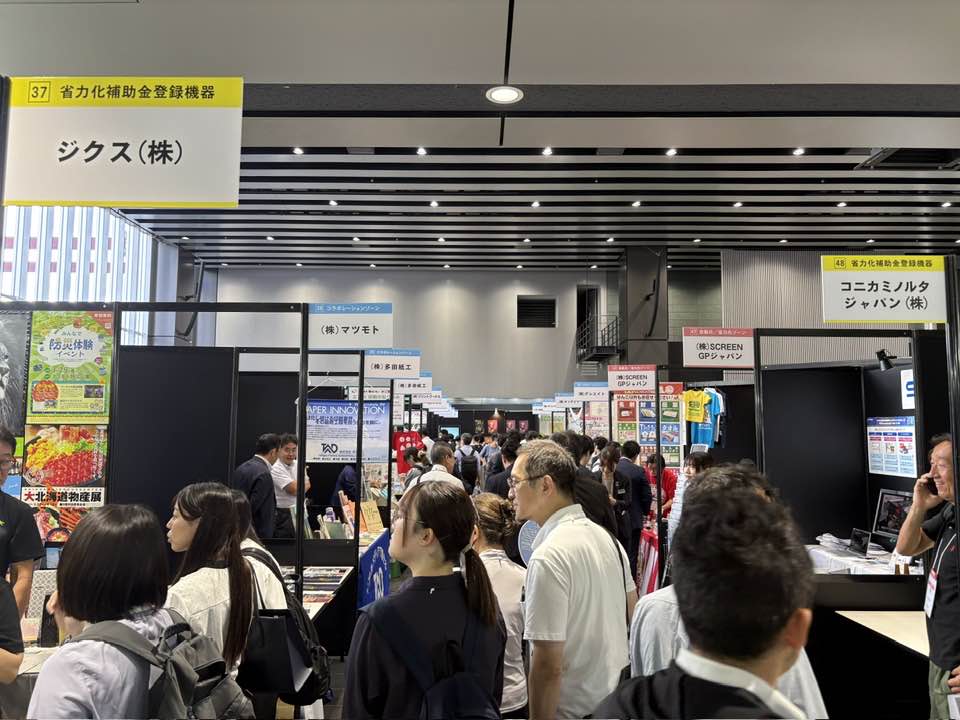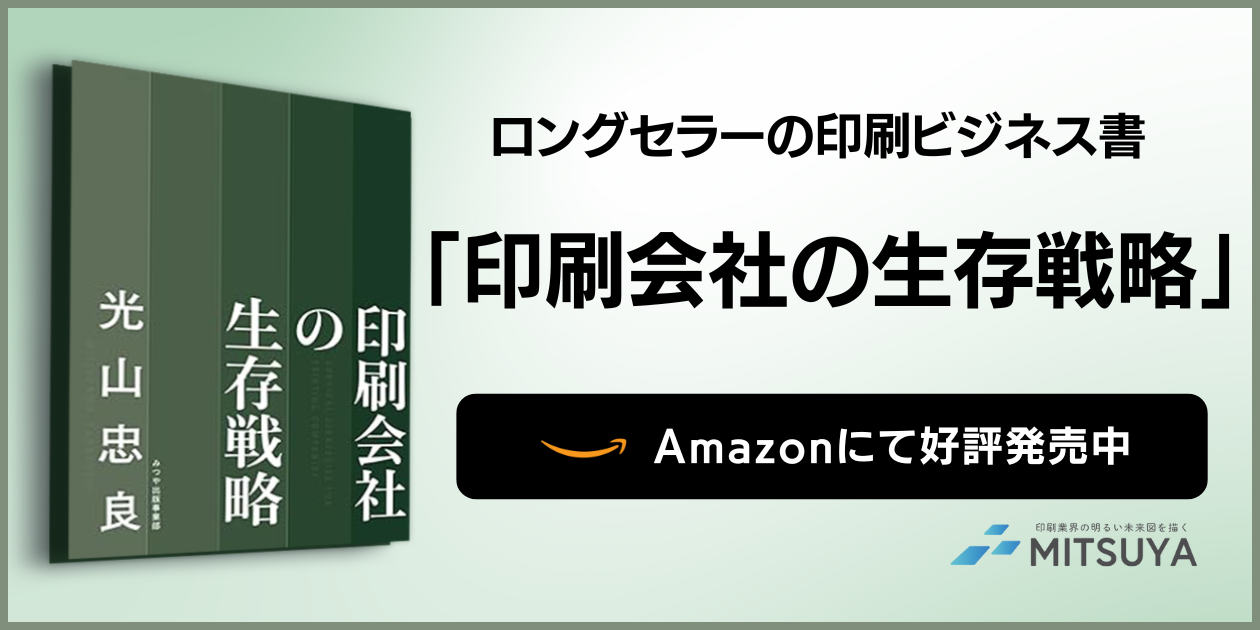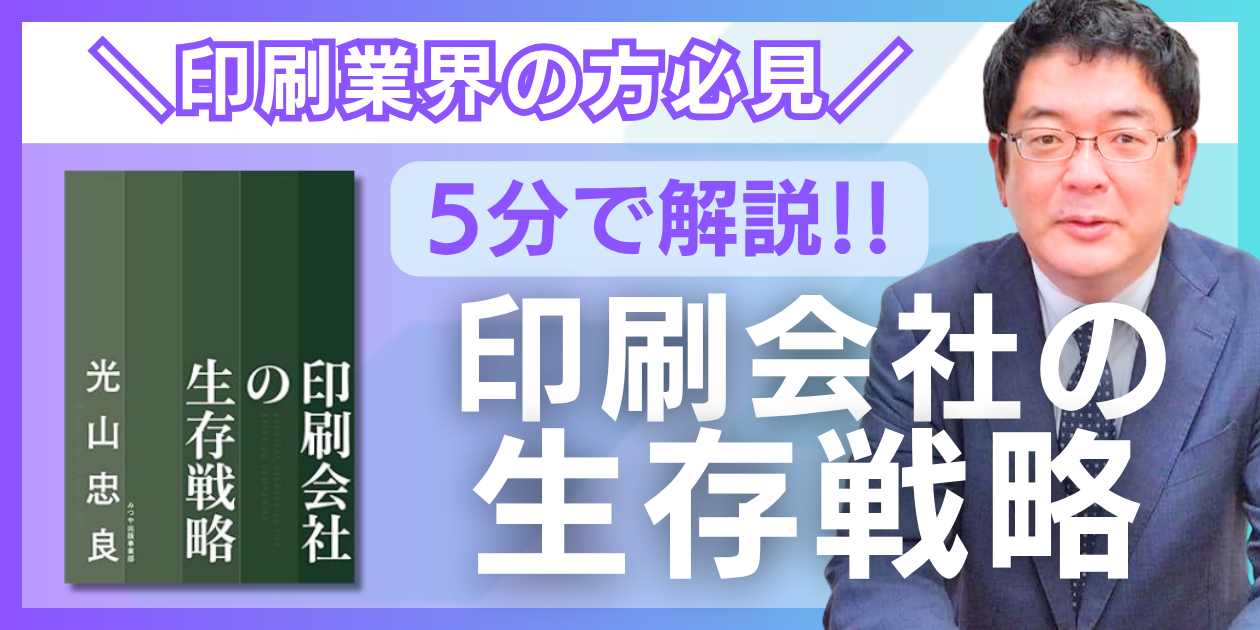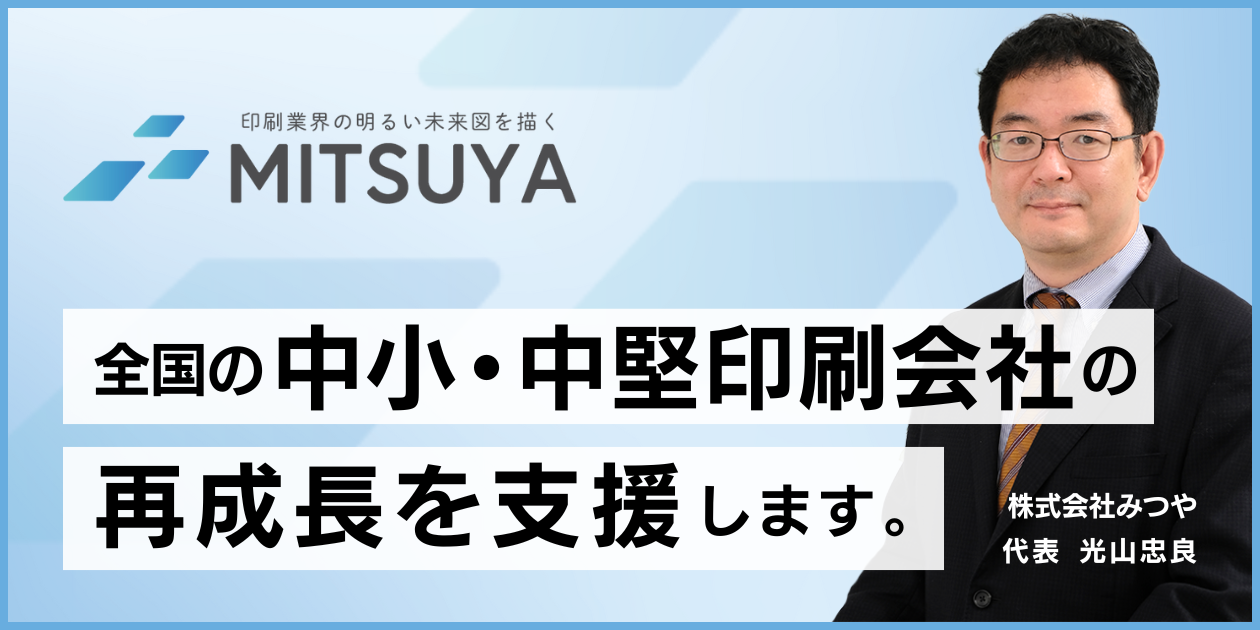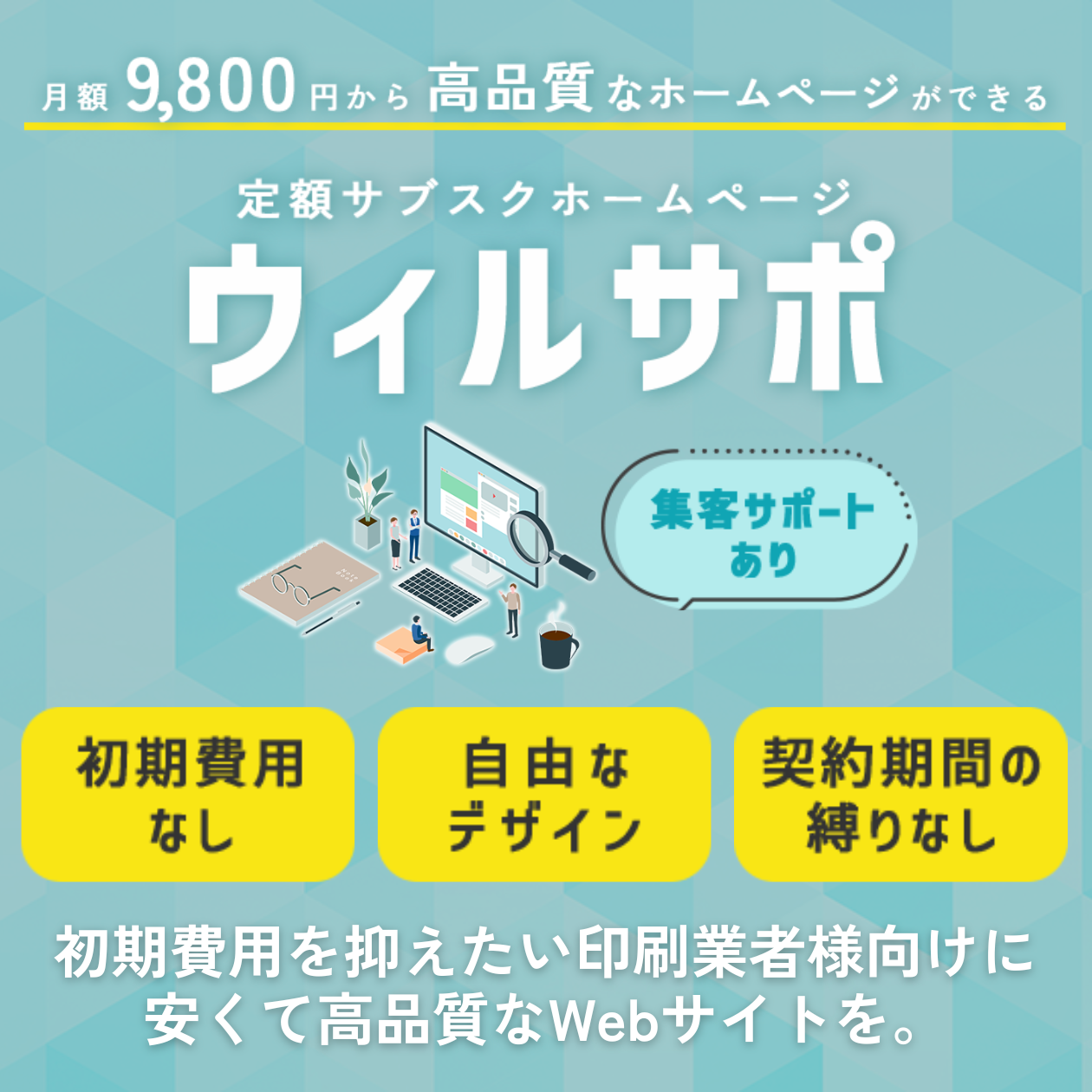ドラッカーとはオランダ語で「印刷人」を意味し、印刷機材展ドルッパとも語源が共通するわけだが、もちろんドラッカーといえばピーター・ドラッカーである。しかし、「マネジメントの父」といわれ、日本でも井深大や柳井正など著名な経営者を魅了してきた彼が、なぜ経営学の入門書にも、中小企業診断士のテキストにも出てこないのか、私の長年の謎であった。そのもやもやの一つの解となったのが井坂康志『ピーター・ドラッカー―「マネジメントの父」の実像』である。
本書でも、日本はもちろんアメリカでも「ドラッカーの著作を学生に読ませたことは一度もなく、またほかの大学でもそのようなことは聞いたことがない」と大学院教授に評され、アカデミックからは乖離していることが紹介されている。
しかしどうやら、ドラッカーを経営学から遠ざけていたのはアカデミック側ではなくドラッカー本人だったようだ。経済学者と呼ばれるのを極度に嫌い、経済を中心とする世界観を断固拒否した。敵対的買収などの利潤追求を激しく批判し、「資本主義そのものに疑義がある」とまで指摘された。シェイクスピアや日本画に傾倒する一方、なんと経営書は一冊も読まなかった。
結局彼は、何者だったのか。一言でいうと、「物書き」だった。晩年本人が「私は一人のライターだ」と言ったように。
彼の著書「断絶の時代」の邦訳を出版したダイヤモンド社の新社屋が「断絶ビル」と呼ばれたように、日本でベストセラーになり、一大ブームを引き起こした。ひょっとしたらドラッカーは100年後には忘れ去られるかもしれない。だが個人的には、ドラッカーを近しく感じる。ジャーナリストであり、取材することを怠らず、書き続けた物書きを、一介のライターである私は尊敬せざるを得ない。どんなに僭越といわれようとも。